ウェブマーケティングに関連する心理学研究結果・マーケティングデータまとめ
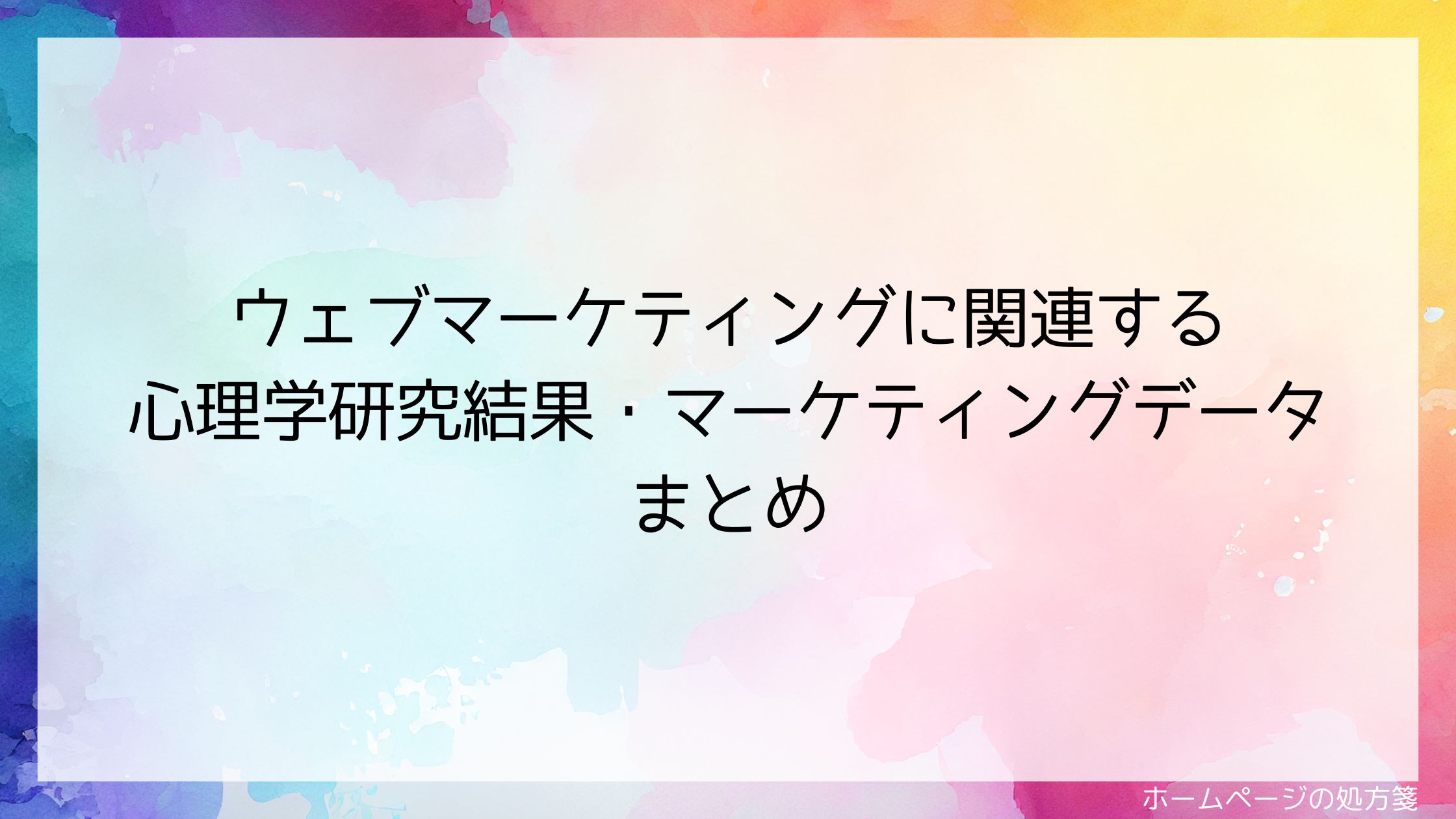
こんにちは!
「どうすればお客様の記憶に残り、好意度を高めてもらえるのか?」
多くのウェブマーケターが頭を悩ませるこのテーマは、実は科学的に裏付けられた方法があります。
心理学やマーケティングの研究を踏まえると、私たちが“記憶にとどめる”仕組みや“好きになる”仕組みを理解し、正しい手法を取ることができるのです。
本記事では、エビングハウスの忘却曲線やヴォン・レストルフ効果、クルーグマンの3回の法則、単純接触効果など、ウェブマーケターなら押さえておきたい代表的な研究を1つずつ詳しく解説していきます。
【本ページの要約】
- 複数回の接触
- エビングハウスの忘却曲線からわかるように、人は放っておくとどんどん忘れてしまいます。複数チャネルやタイミングをずらした接触で、記憶への定着を図りましょう。
- 異質な演出&効果的な順序
- ヴォン・レストルフ効果やプライマシー&レセンシー効果を応用して、ユーザーが「つい目を向けてしまう」設計や、最初と最後に強い印象を残す工夫をしましょう。
- 単純接触効果を活かす
- 繰り返し接触は好感度向上に繋がりますが、飽きには要注意。特に広告摩耗を起こさないよう、クリエイティブやメディアの組み合わせを工夫してください。
1. エビングハウスの忘却曲線(1885年)
エビングハウスの忘却曲線とは?
ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウス(Hermann Ebbinghaus)は、1885年に発表した『記憶:実験心理学への貢献』において、人間がどのように情報を忘れていくのかを世界で初めて体系的に実験した人物です。彼は自作の「無意味綴り」(子音と母音を組み合わせた暗記用語)を用いて、一度学習した情報が経過時間とともにどのくらい思い出しにくくなるのかを詳細に記録しました。その結果導き出されたのが、「忘却曲線(Forgetting Curve)」と呼ばれるグラフです。
エビングハウスの実験によると、人はある情報を学習してから20分後には約42%を忘れてしまい、1日後には約74%を忘れてしまうという衝撃的なデータが得られました。さらに、学習直後から急激に忘却が進行し、ある程度の時間が経過すると忘却のペースは緩やかになるという特徴が見られます。これが「忘却曲線」の基本的な形状です。
しかし同時に、適切なタイミングで復習や再学習を行うと、忘却曲線は緩やかになることも指摘されました。たとえば1日後、1週間後、1か月後など、間隔を空けながら繰り返し情報を思い出したり触れたりすることで、記憶の定着度が上がり、結果的に忘れにくくなるのです。
この知見は学習法だけでなく、マーケティング戦略にも応用できます。
ある情報に触れた後に何もしなければ急速に忘れられてしまいますが、メールマガジンやSNS、広告などを通じてリマインドすることで、記憶を呼び起こし、脳に定着させることが可能になるのです。
特にウェブ上では、ユーザーが1度サイトを離れれば忘れ去られるリスクが高いため、「再度思い出してもらう仕組み」の設計が非常に重要と言えます。
エビングハウスの忘却曲線のマーケティングへの応用例
- 複数チャネルでのリマインド
SNS・メール・広告など多方向から情報を届ける。 - タイミングをずらした接触
エビングハウスの研究が示すように、学習(or 接触)の間隔をあけることで定着率が高まる。 - リターゲティング広告の活用
一度訪れたユーザーへ最適なタイミングで再アプローチする。
2. ヴォン・レストルフ効果(Von Restorff Effect)
ヴォン・レストルフ効果とは
ヴォン・レストルフ効果は、ドイツの精神科医・心理学者であるヘドウィグ・ヴォン・レストルフ(Hedwig von Restorff)が1933年に行った実験に由来します。
彼女は、人間が複数の情報を記憶する際、周りと異なる特徴を持つ「異質な情報」が際立って記憶に残る現象を観察しました。
具体的には、被験者に多数の単語(あるいは記号)を連続的に提示し、そのうち1つだけフォントや色を変えたり、単語のカテゴリーを変えたりすると、後のテストでその「異質な単語」が想起される割合が顕著に高まったのです。
この効果が生まれる理由としては、人間は情報を処理するときに、同質の情報が並ぶ中に突如として現れる「異質」な刺激に対して注意を向けやすいという脳の特性が関係していると考えられています。大量の情報が似通った形式で提示されると、脳はそれらをひとまとめにして処理しようとするため、逆に目立つ要素があると「何だろう?」と自然に意識を向けるわけです。
マーケティングの場面では、たとえば広告バナーがたくさん並ぶウェブページで、1つだけ配色や文言が大きく異なるといったケースが想定されます。ユーザーの視線を集めたい場合には、周囲とあえて“ズラす”設計をすることが効果的。また、メールマガジンの件名や、SNS投稿のビジュアルで他社と大きく違うトーン・スタイルを採用するなども同じ発想です。ただし注意が必要なのは、「やみくもに派手にする」だけではなく、**ターゲット層が受け入れやすい程度の“違い”**を意図的に演出する点です。あまりにも突飛すぎると嫌悪感につながったり、内容と合わずに逆効果になったりします。バランスをとりながら、いかに「異質さ」を加えるかがポイントとなります。
ヴォン・レストルフ効果マーケティングへの応用例
- 広告バナーやLPデザインへの活用
周囲と異なる色使いやキャッチコピーで視線を獲得する。 - メール件名・SNS投稿での差別化
文字数や表現方法に変化をつけ、埋もれない工夫をする。 - 過剰な違和感を避ける
「奇をてらいすぎない」程度のインパクトが重要。
3. プライマシー効果&レセンシー効果
プライマシー効果&レセンシー効果とは
プライマシー効果(Primacy Effect)とレセンシー効果(Recency Effect)は、記憶心理学の分野でよく知られる現象です。これらの研究は、多数の心理学者が繰り返し実験を行ってきたため、厳密に「誰が最初に発見したか」を1名に特定するのは難しい側面がありますが、もともとはハーマン・エビングハウスの研究にも通じるテーマであり、その後、ソロモン・アッシュ(Solomon Asch)らが社会心理学の文脈で「印象形成」におけるプライマシー効果を検討しています。
プライマシー効果とは、リストや文章、会話などで最初に提示された情報が強く記憶に刻まれ、それに後からの情報が影響を受けるという現象です。たとえば、人の性格を説明する形容詞のリストを読み上げるとき、「陽気で、親切で、頭が良くて……」といったポジティブな単語が最初にくるほど、その人への好印象が高まる傾向があります。一方で、最初にネガティブな言葉が並ぶと、後のポジティブな情報が入ってきても印象が悪くなりがちです。
レセンシー効果はその逆で、直近で提示された情報を特に記憶しやすいという性質を指します。たとえば、長いリストの最後に出てきた単語は覚えやすいといった実験結果が数多く報告されています。また、アンケートやプレゼンテーションの最後で印象的なメッセージを伝えると、その後も記憶に残りやすいです。
これら二つの効果は共通して「情報提示の順序」が記憶や印象形成に大きく影響を与えることを示しています。マーケティングにおいては、LP(ランディングページ)の冒頭や締めくくり、メールマガジンの「件名」「最終段落」など、ユーザーが特によく目を通す部分に優先的に重要な情報を配置すると効果が高まると考えられます。逆に、中盤の冗長な部分は飛ばされる可能性があるため、キャッチコピーやまとめ部分に訴求ポイントを盛り込み、記憶に残す工夫が求められます。
プライマシー効果&レセンシー効果のマーケティングへの応用例
- ウェブサイトやメディアなどの第一印象を整える
第一印象を整えて、重要なメッセージやCTAを配置する。 - ウェブサイトやLPのファーストビューの最後も重要視
ここにメインメッセージやCTAを配置する。 - 商品紹介やプレゼン資料の構成
初頭と結論部分で印象付けたい情報を強調する。 - 中盤の“退屈ゾーン”対策
適度に見出しやビジュアルを入れ、離脱を防止する。
4. 単純接触効果(ザイアンスの法則)
単純接触効果(ザイアンスの法則)とは
単純接触効果(Mere Exposure Effect)は、アメリカの心理学者ロバート・B・ザイアンス(Robert B. Zajonc)が1968年に発表した研究で広く知られています。
この研究では、参加者に無意味な単語や漢字のような未知の文字を何度か見せ、その文字に対して抱く感情的評価を調べました。すると、繰り返し見せられた文字ほど「好ましい」「親しみがある」と評価する傾向が明確に示されたのです。ザイアンスは、このように「よく見る対象を好むようになる」現象を単純接触効果と呼びました。
背景には、人間の脳が「見慣れたもの・安全なもの」を好む性質があると考えられています。
初めて遭遇する対象には警戒心や不安を抱きやすい一方、繰り返し触れ合ううちに「この対象は危険ではない」と学習し、次第に好意的な反応を示すようになるわけです。これは心理学の進化論的な視点からも説明されることが多く、人間や動物が未知の対象を警戒し、慣れた対象を安全と見なす傾向に起因すると言われます。
マーケティングの世界では、広告やSNS投稿などで同じブランド名やロゴを見せ続けると、最初は興味がなくても徐々に親しみや好感度が上がる効果が期待できます。ブランド認知を高めるうえで非常に有用な理論であり、大企業がテレビCMを高頻度で流す背景にも、この単純接触効果の概念があります。ただし、注意すべきは「過剰接触」による飽きや嫌悪感(広告摩耗)です。単純接触効果は確かに有効ですが、同じクリエイティブを連打しすぎると逆効果になりかねません。適度なバリエーションや、接触頻度のコントロールが求められます。
単純接触効果(ザイアンスの法則)の応用例
- ブランドロゴやカラーの一貫性
あちこちで目にするうちに「親しみ」を感じてもらえる。 - SNS配信や広告の継続露出
定期的に情報発信することで認知度と好感度を高める。 - 飽き対策
クリエイティブを変更したり、適切な頻度に調整したりする。
5. ツァイガルニク効果
ツァイガルニク効果とは
ツァイガルニク効果(Zeigarnik Effect)は、ソビエト連邦出身の女性心理学者ブリューマ・ツァイガルニク(Bluma Zeigarnik)が1927年に発表した研究に基づくものです。彼女は、当時ウィーンの心理学研究所でレストランの給仕(ウェイター)が、「精算が済んでいない注文(未完了のタスク)」ほど細かく覚えている姿に興味を抱きました。これを実験で検証するため、被験者に単純な作業やパズルを行わせ、一部の被験者は作業を途中で中断させ、一部は最後まで完了させました。その後、どの課題をよく覚えているかを尋ねると、中断された課題(未完了)の方が印象に残っているという結果が得られたのです。
この現象の心理的メカニズムとしては、人間が**「完了していないもの」や「未解決のまま残っている問題」に意識を向けやすく、モヤモヤや不完全感を解消しようとする**性質があるからだと説明されます。途中でストップした作業や解決していない疑問は頭の中で継続的に処理され続けるため、自然と意識が向き、記憶にも残りやすいのです。
マーケティングへ応用する場合、**「続きはウェブで」「次回はもっと詳しく説明」「カートに商品が残っています」**といった形で、意図的に“未完了”状態を作り出すことが有効です。映画の予告編や新商品のティーザー広告も、まさにこの効果を活かしたものと言えるでしょう。ユーザーに「最後まで見たい」「早く完結させたい」と思わせることで、自発的に情報へアクセスしてもらったり、購入まで導いたりする狙いがあります。ただし、あまりに中断のタイミングや煽り方が不自然だとストレスや不快感を与える恐れがあるため、自然な形で興味をつなぎ留める設計が大切です。
ツァイガルニク効果マーケティングへの応用例
- ティーザー広告や予告動画
途中まで見せて「続きは○月○日に公開!」と期待感を煽る。 - カート落ち対策
購入手続きを“未完了”にしているユーザーへリマインドメールを送る。 - 連載コンテンツ
ブログやSNSで「次回に続く!」と結んで、定期的に読みに来てもらう。
6. クルーグマンの3回の法則
クルーグマンの3回の法則とは
ハーバート・E・クルーグマン(Herbert E. Krugman)は1970年代にテレビ広告の効果に関する研究を行い、「広告接触は最低3回必要」という理論を提唱しました。これは、消費者が広告を目にするプロセスを大きく3段階に分解して考えるという考え方です。すなわち、「1回目は“認知”して興味を引かれる」「2回目は“理解”してどんな商品かを把握する」「3回目で“納得”や“行動”に結びつく」という流れがあるとされています。
背景には、消費者が広告に触れたときの心理的変化を段階的に捉えようとした点があります。1回目で「これは何だろう?」と疑問を持ち、2回目で「ああ、あれか」と記憶を呼び起こし、3回目で「いいかもしれない」「買ってみようかな」と具体的な行動を検討する、というわけです。この理論はテレビ広告のみならず、今日のデジタル広告にも応用可能とされ、特にバナー広告やリマーケティング広告などで複数回露出させる戦略につながっています。
ただし、現代の消費者は多種多様なメディアや情報に触れているため、一概に「3回だけで十分」とは言えません。あくまで**「最低3回は必要」という目安**と捉えるのが妥当です。加えて、商品やサービスの種類、ターゲット層、広告のクリエイティブの質などによって、最適な接触回数は変動します。重要なのは、繰り返し接触を設計しつつ、飽きさせない多様なクリエイティブやメッセージを提供することで、3回を超えた接触でも嫌悪感を持たれないようにすることです。
クルーグマンの3回の法則マーケティングへの応用例
- 広告配信のプラン設計
ターゲット1人あたり、少なくとも3回は広告接触を狙う。 - ストーリー仕立ての展開
1回目→2回目→3回目とステップを踏んで、理解から納得へ導く。 - フリークエンシーキャップ
の活用: 過剰接触にならないよう回数をコントロール。
おわりに
いかがでしたか?
心理学とマーケティング研究が教えてくれる「人が覚える仕組み」「好きになる仕組み」を知ると、今まで感覚的にやっていた施策に科学的な裏付けを持たせることができます。大事なのは、これらの知見を鵜呑みにするだけでなく、実際のデータや自社の顧客特性を踏まえて「どのくらいの頻度・タイミング・チャネルが最適か」を探ること。過剰接触やクリエイティブのマンネリ化に気をつけながら、上手にブランディングと販促を両立させましょう。
関連記事:接触回数過剰によるリスクとブランド想起
