記事構成テンプレート付き| 読まれるオウンドメディアの書き方
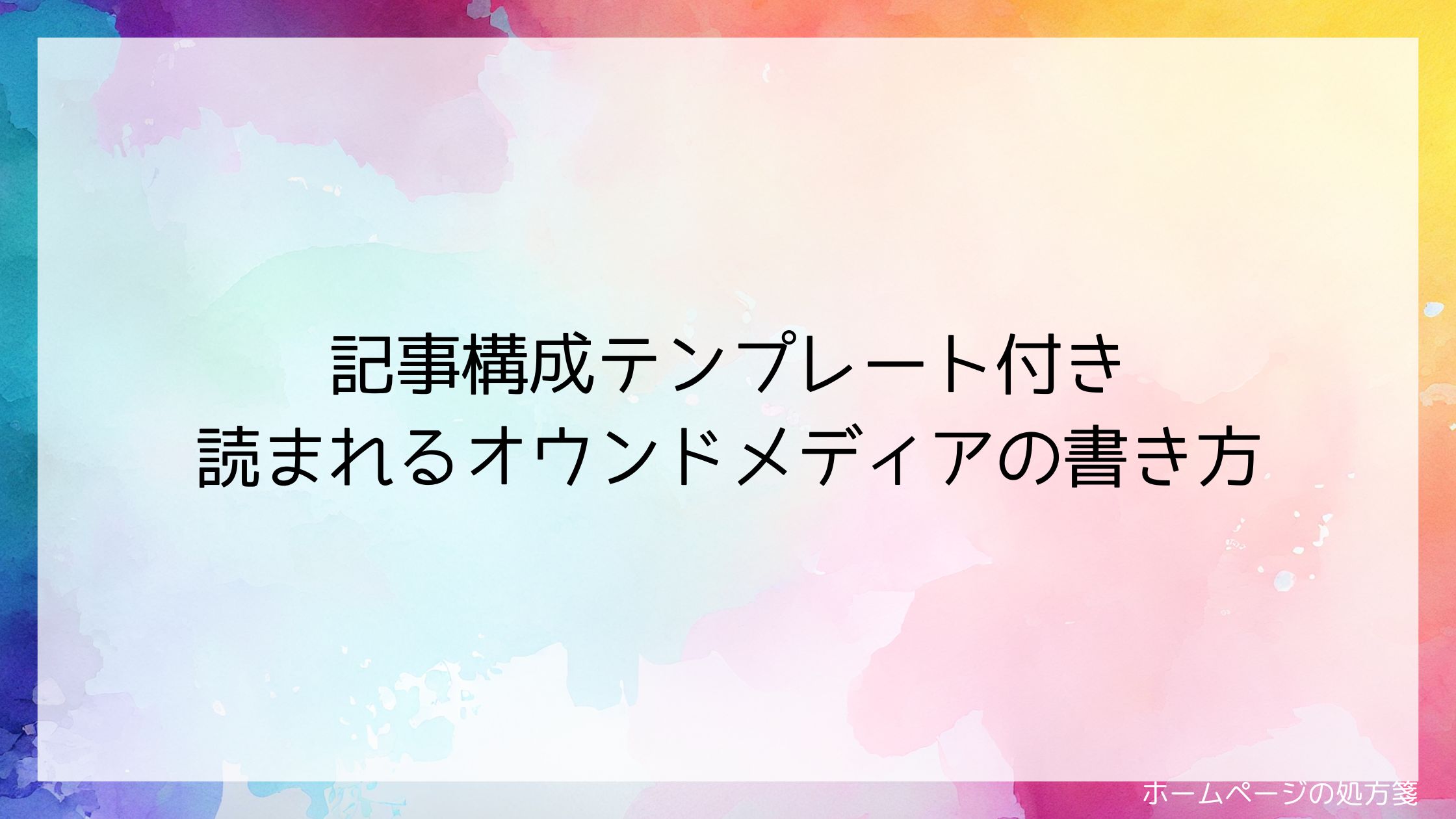
オウンドメディアを成功させるならば、より多くの人に読まれる記事にしたいと思うのは当時です。
ところで、「読まれる記事」とはどういうことでしょうか。
「読まれる記事」とは何か?
読まれる記事とは、大きく分けて3点の記事から読まれます。
SEOの視点(検索経由で読まれる)、SNSの視点(シェアされて読まれる)、ユーザー体験の視点(読者が離脱せず読み進めてくれる)の3つです。
SEOの視点: 検索で上位表示され、ユーザーに読まれる
検索エンジン最適化(SEO)の観点では、読まれる記事=検索結果で上位表示されクリックされる記事です。
Googleなどは「信頼性が高く有益でわかりやすい情報」を高く評価し、ユーザーの検索意図に合った質の高いコンテンツを上位に表示します
しかし、上位に表示されただけでは不十分です。
実際に読者が内容を「役に立った」と感じることが重要で、そうでない記事はすぐ離脱され結果的に順位が下がる傾向にあります
逆に読者満足度が高ければ滞在時間や回遊率が上がり、検索順位も維持・向上しやすくなるのです。
つまりSEO視点で「読まれる」とは、検索上位かつ内容がユーザーのニーズを満たし最後まで読まれる記事と言えます。
SNSの視点: 思わずシェア・クリックしたくなる魅力がある
SNS上ではタイムラインを高速スクロールする中で目に留まり、シェアされる記事が「読まれる記事」です。多くのユーザーは投稿を1~2秒で判断するため、タイトルや冒頭文で一瞬で内容と読むメリットを伝える必要があります。
具体的には、タイトルに数字・ベネフィット・悩み解決などを盛り込んで興味を引くことが有効です。
SNSでは全文を読む前にタイトルとOGP画像、最初の一文程度しか見られないため、そこで「これは自分に役立ちそう」「面白そう」と思わせられればクリックやリツイートにつながります。
さらに、役立つ情報だけでなく共感や驚きなど感情を揺さぶる要素もシェアを促進します。
SNS視点で「読まれる」とは、思わず人に教えたくなる魅力を備えた記事だと言えるでしょう。
ユーザー体験の視点: 読みやすく満足度が高い
読者が実際にページを開いてから最後まで目を通すかどうかは、コンテンツの体験次第です。読みやすさは非常に重要で、段落が長すぎず適度に改行や箇条書きがあること、専門用語は噛み砕いて説明すること、スマホでもストレスなく読める表示になっていることなどがポイントです。文章だけが延々と続くと「読みづらい…」と感じて離脱されかねません。
記事全文ではなく冒頭とまとめだけ読む人も少なくありません。
そのため最初と最後に記事の要点を配置しておくことで、「ざっと読んだだけでも得るものがあった」と感じてもらいやすくなります。
ユーザー体験の観点で「読まれる」とは、ストレスなく読み進められて有益な情報が得られる記事です。
以上の3視点を踏まえ、次章から具体的な記事の書き方を5つのパートに分けて解説します。
読まれる構成とは
ここでは「タイトル」「導入」「本文」「まとめ」「CTA」の各パートごとに、役割と書き方のコツを紹介します。
まずはオウンドメディア記事の基本構成を確認します。
一般的に記事は以下の5つのパートで構成され、それぞれに役割があります。この構成を意識することで、記事全体が論理的かつ読みやすくなります。
| タイトル | 記事の顔。 読者と検索エンジン双方に内容を伝え、興味を引く。 一目で「誰のための何の記事か」が分かる具体的なタイトルにする。 (例:「初心者向け○○のやり方5選|すぐ実践できる○○のコツ」) |
|---|---|
| 導入文 | 記事の導入部分(リード文)。 読者の悩みや課題に共感し、この記事を読むメリットや要約を提示する。 シンプルに記事全体の概要を述べ、続きを読みたいと思わせる。 (例:「○○でお困りではありませんか?本記事では○○のポイントを解説します。」) |
| 本文 | 記事の主本文。 見出し(H2/H3)ごとにトピックを整理し、詳細な情報や解決策を提示するパート。 箇条書きや図解も用いながら、読者の疑問を一つひとつ解消する。 セクションごとに完結した内容にし、網羅的かつ読みやすく展開する。 |
| まとめ | 記事全体のまとめ。 本文の要点を簡潔に振り返り、記事で伝えたかった結論や示唆を述べる。 読者が学んだことを再確認し、「結局何をすべきか」が分かるようにする。 (例:「○○のコツは△△と□□です。ぜひ今日から実践してみましょう。」) |
| CTA | 行動喚起部分。 記事を読んだ読者に取ってほしい行動を促す締めくくり。 自社サービスの紹介や資料請求・問い合わせへの誘導、関連記事の案内、SNSフォローのお願いなどを具体的に提示する。 読者にとって自然で魅力的なアクションを提示することが重要。 |
それでは、上記の各パートについて順番に詳しく見ていきましょう。
1. タイトル:読者の興味を引き検索にも強い見出しをつける
記事のタイトルは最も重要な要素です。タイトル次第でクリックされるかどうかが決まると言っても過言ではありません。
タイトルの役割
記事の内容を端的に表す「顔」です。検索結果ページではタイトルがまず表示されるため、SEO的には主要キーワードを含めつつ内容の関連性を示す必要があります。
同時にSNS上ではタイトルがユーザーの興味を引くコピーとして機能します。
つまりタイトルは検索エンジンへの最適化と読者への訴求を両立させる必要があります。
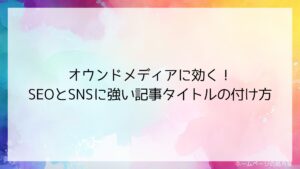
2. 冒頭文:冒頭で読者をつかみ記事の価値を伝える
冒頭文(リード文)は本文に入る前のつかみの部分です。ここで読者の心をつかめないと、その先を読んでもらえません。最初の1~2文で興味を引き、記事全体の要旨を伝えることが導入の役割です。
冒頭文の役割
読者に「読み進める動機」を与えることが導入文の使命です。
具体的には、「あなたの悩みを理解しています、この先に解決策がありますよ」と示す場面です。検索から来た読者には「このページにはあなたの求める答えがあります」と、SNSから来た読者には「面白そうだから続きを読んでみよう」と思わせる役割があります。
また導入は記事全体の要約でもあるため、読者にとってのメリット(ベネフィット)を簡潔に盛り込むと効果的です。
導入文は記事全体の案内役です。読者の関心をグッとつかみ、「この先には自分のためになる情報がある」と期待させる導入を心がけましょう。
特に昨今はスマホで流し読みする読者も多いため、短く箇条書き的に要点を示すくらいがちょうど良いかもしれません。
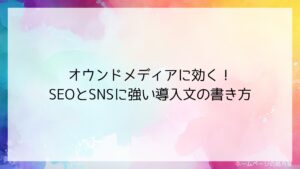
3. 本文:情報を整理し読みやすく価値あるコンテンツを提供する
本文は記事の本体であり、一番ボリュームのあるパートです。
読者の悩みや疑問に答える具体的な情報を提供し、価値を感じてもらうことが本文の役割です。ここでは本文全体の構成や書き方のポイントを解説します。
本文の役割
読者が知りたいことに答え、問題を解決する核心部分です。
タイトルや導入で提示したテーマについて、詳細な解説や手順、事例などを示して読者の知識欲求を満たします。
検索ユーザーにとっては検索意図そのものに答える部分であり、SNS経由の読者にとっては興味深い情報や共感できる内容を提供する部分です。
本文が充実していれば、その記事は読者にとって価値のあるものとなり、結果的にSEO評価も高まります。
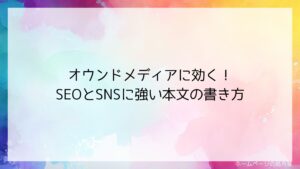
4. まとめ:記事の要点を再確認し読者に次のアクションを促す
「まとめ」は記事全体の締めくくり部分です。本文で述べたポイントを読者の頭の中で整理し直す役割があります。
また次に述べるCTAと組み合わせて、読後の読者をスムーズに次の行動へ誘導する重要なパートです
まとめの役割
記事の要約と結論を伝えることが第一の役割です。
長い記事であれば特に、最後に要点をまとめてあげることで「結局何が大事だったのか」が読者にはっきり伝わります。
第二に、読者に次の行動を促す役割も持ちます。
まとめは読まれやすい箇所なので、そこで記事を読んだ上で取ってほしい行動(商品購入や問い合わせ、別記事への誘導等)に言及すると効果的です。
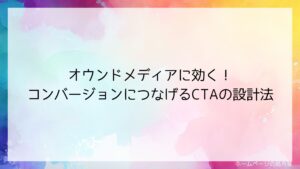
5. CTA:読者に具体的なアクションを促す締めのひと押し
CTA(Call To Action)は直訳すると「行動喚起」です。記事の末尾に設置することが多く、読者に何らかのアクションを起こしてもらうための呼びかけを指します。マーケティング目的のオウンドメディアではCTAまで含めて記事と言えます。
CTAまで含めることで、記事はビジネス成果につながるコンテンツとなります。せっかく読者の関心を掴んだのなら、次のアクションへスムーズに誘導してあげることが親切でもあります。まだCTAを設置していない方は、この機会に記事の末尾に一言付け加えてみてはいかがでしょうか。各パートのポイントを押さえた構成で、ぜひ読まれる記事作りを実践してみてはいかがでしょうか。
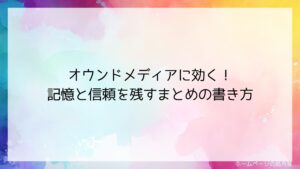
まとめ
記事の内容がどれほど素晴らしくても、構成が悪ければ読まれずに終わってしまう可能性があります。 タイトル、導入、本文、まとめ、CTA——それぞれに目的と設計のコツがあります。
まずはこの5つのパートを意識し、ひとつずつ丁寧に設計してみてはいかがでしょうか。
 ウェブマーケター
ウェブマーケターお困りの際はぜひ一度ご相談ください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
