雑誌?ブログ?Web記事?オウンドメディアの種類と特性を経営者の視点で読み解く
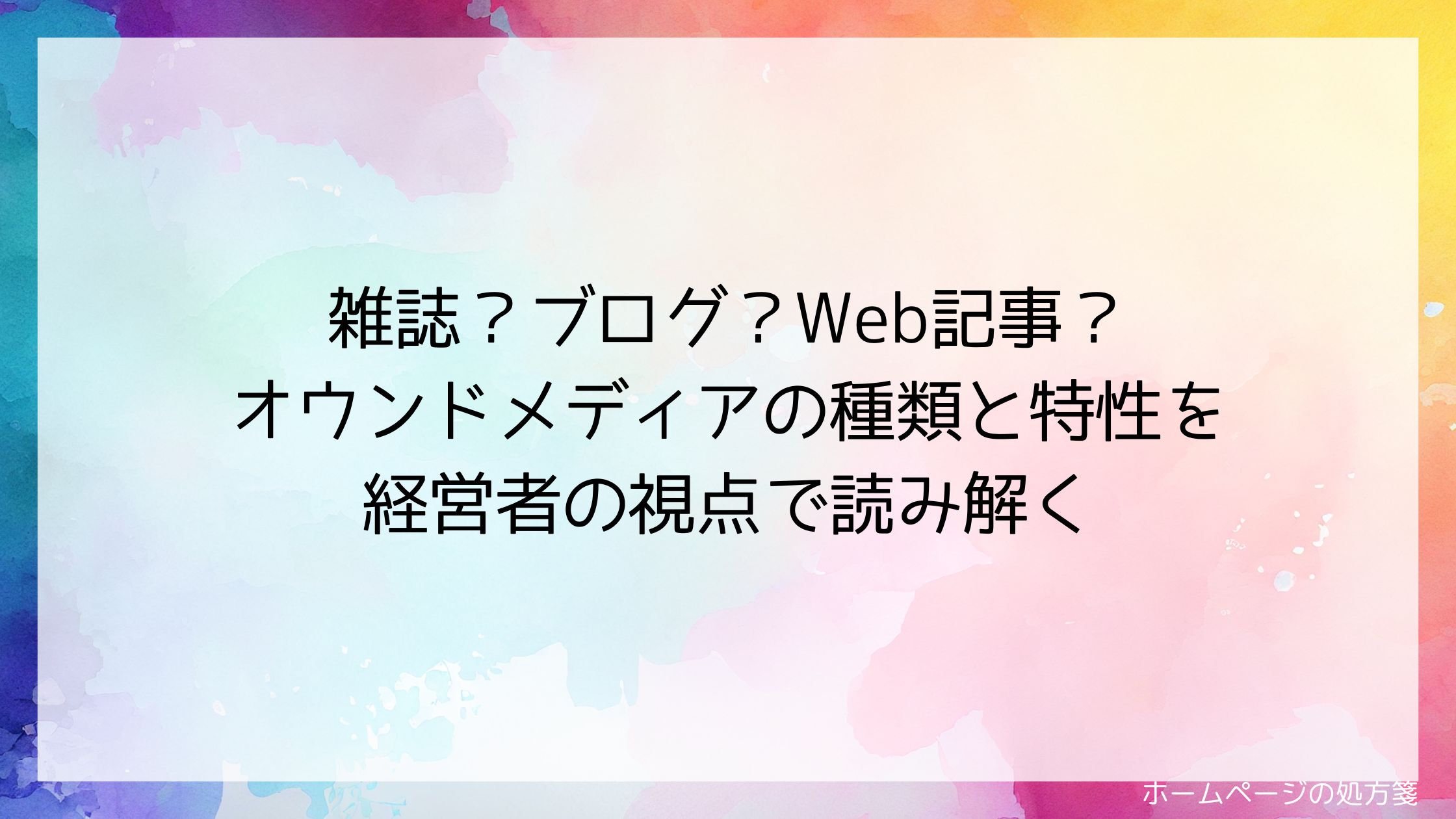
オウンドメディアを立ち上げる際、どのような形式にするかは戦略設計の重要なポイントです。
ブログ形式で始めるのか、雑誌風に編集された読み物にするのか、特定のテーマに特化した特集サイトにするのか。それぞれにメリット・デメリットがあり、目的や運用体制によって適した形式は異なります。
この記事では、主なオウンドメディアの形式を分類し、経営者視点でその特性や活用の方向性を整理します。
オウンドメディア5つの型
ブログ型オウンドメディアとは
ブログ型は、社員による定期的な投稿によって情報発信を継続できる形式です。
比較的始めやすく、SEOにも効果があるため、集客や信頼形成に有効です。自社ノウハウの蓄積や、継続的な更新によってファン層を育てるのに適しています。
想定されるゴール:月間アクセス数の向上、検索流入の増加、ナーチャリングによるリード獲得
KGIの例:月間オーガニック検索流入3000件、メルマガ登録数100件
雑誌型オウンドメディアとは
雑誌型は、企画・編集を重視し、特集やインタビューなど読み物性の高いコンテンツで構成される形式です。
ブランドイメージの訴求や理念の発信、業界における立ち位置の確立などに有効です。
読者との関係性を深める長期的な施策として用いられます。
想定されるゴール:企業への共感醸成、認知の広がり、採用ブランディング
KGIの例:ブランド想起率50%、採用応募者のうち自社メディア経由20%
記事型LPオウンドメディアとは
記事型LPは、商品やサービスの魅力をストーリー仕立てで訴求する形式で、広告やSNSからの流入を前提とした直接的なコンバージョン獲得を狙います。
個別記事単体で成果を出す設計に適しており、プロモーションキャンペーンと相性が良い形式です。
想定されるゴール:資料請求、無料相談申込みなどのCV獲得
KGIの例:記事経由のCV数月50件、LP経由成約率5%
ハブサイト型オウンドメディアとは
ハブサイト型は、複数のサービスや事業部門が存在する企業に向いており、それらの情報を体系的に整理・配信するポータル型のメディアです。
事業別・顧客別に情報導線を整理できるため、企業全体の価値を俯瞰的に伝えることができます。
想定されるゴール:ブランド全体の理解促進、部門間横断の相互流入、複数商材の導線統合
KGIの例:訪問者の平均ページ閲覧数3.5、ハブサイト経由のサービス比較閲覧数月100件
メディアの形式は単なる見た目ではなく、運用目的や読者との関係性、社内リソースの状況に直結する戦略的要素です。
| 種類 | 代表的な形式 | 特性 | 向いている目的・業種 |
|---|---|---|---|
| ブログ型 | WordPressブログ、社員執筆記事 | 継続投稿、柔軟性が高い | SEO対策、継続集客、社内発信文化の育成 |
| 雑誌型 | オンラインマガジン、テーマ特集、インタビュー連載 | 企画・編集重視、読者との関係性構築 | ブランド浸透、理念訴求、業界啓発 |
| 記事型LP | 特定サービス紹介記事、成功事例まとめ | CV重視、直接訴求力が高い | 商談獲得、サービス認知 |
| ハブサイト型 | 複数の事業・テーマ別に分岐した構造 | 専門性の整理、ポータルとしての活用 | 複数商材・多部署連携 |
それぞれの形式で注意すべきポイント
ブログ型オウンドメディアの注意点
- 継続更新が前提となるため、更新が止まると印象が悪くなる
- 社内に書き手がいるかどうかが継続のカギ
- SEOに有利だが、テーマの一貫性が必要
- 例:社内ニュース、製品に関するノウハウ、業界解説コラム、社員ブログ、導入事例紹介など
雑誌型オウンドメディアの注意点
- 編集スキルやコンテンツ制作体制が求められる
- ブランド構築には強いが、成果が出るまでに時間がかかる
- 特集ごとの企画力と取材力が成否を分ける
- 例:ストーリーテリング重視の事例集、社会課題を扱う啓発型読み物、対談形式の連載記事など
- 例:企業理念やストーリーを掘り下げる連載、インタビュー特集、業界課題の深掘り記事など
記事型LPオウンドメディアの注意点
- 記事単位では読まれやすいが、メディア全体としての構造は薄くなる
- 広告やSNSでの集客とセットで使うと効果的
- 直帰率が高くなりがちなので導線設計が重要
- 例:キャンペーン紹介、サービス詳細記事、顧客事例による訴求型コンテンツなど。たとえば新サービスのリリース時に広告流入とセットで集客し、読者に商品の価値や他社との違いをわかりやすく伝えるといった活用が想定される
- 例:キャンペーン紹介、サービス詳細記事、顧客事例による訴求型コンテンツなど
ハブサイト型オウンドメディアの注意点
- 情報量が多くなるため、構造設計・ナビゲーション設計が重要
- 組織内の調整が必要になる
- ブランドごとの違いが明確であるほど効果的
- 例:複数の事業やブランドを展開している企業が、それぞれの紹介ページを統合した情報ハブとしてのメディア。製品カテゴリ別に分岐させるサイト構造や、用途別に導線を整備した事業紹介ポータルなど
- 例:複数事業を持つ企業が、製品別・顧客別に情報を整理した統合ポータルサイトなど
よくある質問
- オウンドメディアはブログ形式が主流なのでは?
-
たしかに導入しやすく、中小企業にも普及していますが、それだけが正解ではありません。ブランド価値や読者体験を重視するなら雑誌型、商談目的なら記事LP型が有効な場合もあります。
- 雑誌型は見た目だけ立派で成果につながらないのでは?
-
編集設計と導線設計次第で、見込み顧客の信頼やリード獲得にもつなげられます。読者との関係を深める中長期戦略です。
- 形式を変えたらリニューアルコストがかかるのでは?
-
初期段階で戦略を整理していれば、将来的な拡張や段階的な移行もスムーズです。構成設計を柔軟にしておくことがポイントです。
まとめ|形式に正解はない、戦略と目的で選ぶ
オウンドメディアの形式には明確な正解があるわけではありません。
企業の目的、リソース、伝えたい世界観によって選ぶべき形式は異なります。
読者との関係性をどう築くか、どこに成果を求めるかを明確にし、自社に最適な形式を見極めてみてはいかがでしょうか
 ウェブマーケター
ウェブマーケターお困りの際はぜひ一度ご相談ください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
