アフターデジタルとは? ビフォアデジタルとのちがいと企業の取り組みを学生にもわかりやすく解説
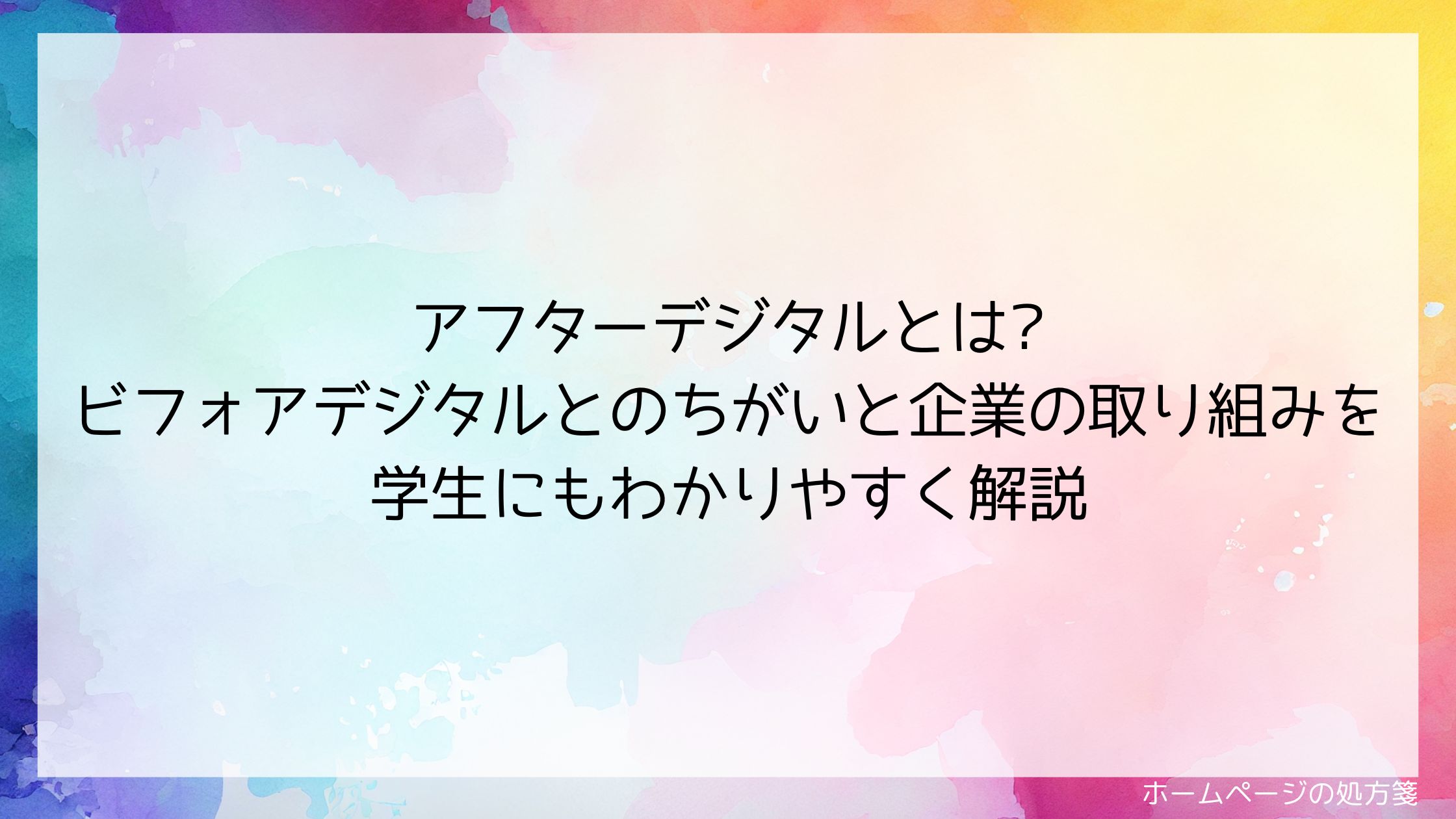
 ウェブマーケター
ウェブマーケターこんにちは。ウェブマーケティングの専門家、井水です。
アフターデジタルという言葉を聞いたことがありますか。
これは、スマホやインターネットなどのデジタル技術がすごく当たり前になって、オンラインとオフラインの区別があまりなくなった状態を表しています。
企業では、この状態に合わせてビジネスのやり方を変えており、ホームページの役割も大きく変わっています。



ここでは、アフターデジタルがどういうものか、ビフォアデジタルとどんなちがいがあるのかをやさしく説明します。
アフターデジタルとは
アフターデジタルは、デジタル技術が社会にしっかり浸透したため、オンラインとオフラインの線引きがあいまいになった状態を指します。
たとえば、日常生活でいつでもスマホを使い、お店で買い物するときもスマホ経由でクーポンを受け取ったり、支払いをしたりするようなシーンが増えました。
オンラインで得た情報がそのままオフライン(実店舗やリアルな生活)とつながることが普通になってきたのです。
アフターデジタルを言い出したのは、誰?
アフターデジタルという言葉は、日本の企業であるビービットの藤井保文さんたちが提唱しています。
著書などで「これからはオフラインとオンラインの区別がなくなる世界になる」と指摘していて、それをアフターデジタルと呼んでいます。
アフターデジタルを英語圏ではどう表現するか
英語圏でも、アフターデジタルと似たような概念を表す言葉があります。
たとえば、
・digital-first world
・post-digital era
・embedded digital
・seamless digital
などです。
どれも、デジタル技術が特別ではなく、普段の生活の中心になっている状態を指します。
ビフォアデジタルとアフターデジタルのちがい
下の表は、ビフォアデジタル(以前のやり方)とアフターデジタル(今のやり方)のホームページ活用のちがいをまとめたものです。
ビフォアデジタルとアフターデジタルの比較はこちらです。
| ビフォアデジタル | アフターデジタル |
|---|---|
| 情報発信の場 | 顧客体験の場 |
| 企業やお店の情報を一方的に載せる | 利用者が何を求めているかをもとに、使いやすく工夫 |
| オフライン補助 | オンラインとオフラインの融合 |
| お店の場所や営業時間など、実店舗の情報を補足する程度 | 実店舗での行動も記録し、ネット上で活用(逆もあり) |
| 更新は不定期 | 継続的な改善 |
| ときどき情報を追加するくらい | データを集めながら、ホームページをよくしていく |
| 一方向のやりとり | 双方向のコミュニケーション |
| お客さんとのコミュニケーションが少ない | SNSやチャット機能を使い、リアルタイムでやりとり |
このように、ビフォアデジタルの時代は企業が情報を載せておけばいいという感じでしたが、アフターデジタルでは、利用者の行動や好みに合わせてホームページを作りこみ、常に改善しながら使いやすくしていくのが当たり前になっています。
アフターデジタルを通じて、企業にどんな影響がでた?
アフターデジタルの社会では、企業はもっと利用者と深くつながる必要があります。具体的には、次のような点が挙げられます。
データを活用したサービス
オンラインとオフラインの行動データを分析して、利用者が本当に欲しい情報やサービスを見つけ出し、それをホームページやアプリで提供します。
顧客体験の向上
商品の品質だけでなく、利用者がネット上や実店舗でどんな体験をするかも重視します。カスタマイズされたおすすめ情報や、チャットサポートなどで利用者と継続的に関係を築きます。
迅速な意思決定
データをもとに「このページが読まれていない」「この商品が人気」などをリアルタイムで把握し、その情報を活かしてすぐに改善策を打ち出すのです。
まとめ
アフターデジタルとは、オンラインとオフラインの境目が薄れ、ネットが生活の真ん中にある時代です。
ビフォアデジタルのころは、ホームページは企業が情報を載せておく程度のものだったかもしれませんが、今では利用者と長く深いつながりを作るための大事な道具になっています。
これが「アフターデジタル」と呼ばれる世界でのホームページの活用方法です。



やり方がわからないなど、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
