オウンドメディアのアクセス数に一喜一憂してはいけない理由―本質的な分析指標とは―
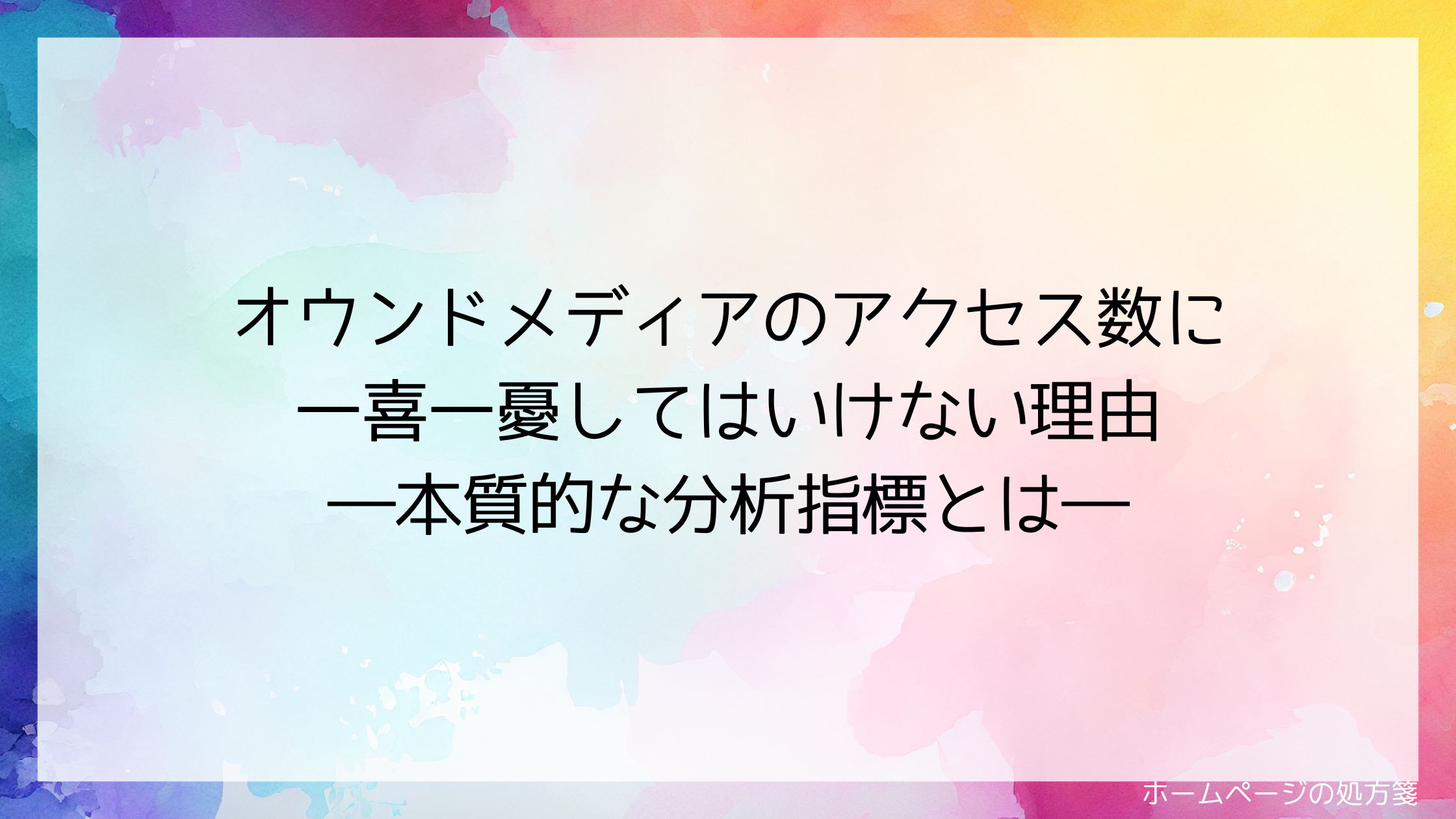
オウンドメディアを運用していると、どうしても日々のアクセス数に目がいきがちです。
「昨日より減った」「思ったほど伸びていない」と、一喜一憂してしまうこともあるでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
そのアクセス数、本当にメディアの“価値”を表していると言えるでしょうか?
アクセス数は目的ではなく通過点
アクセス数は重要な指標のひとつですが、それだけでメディアの貢献度を判断するのは危険です。
特に「資産としての信頼構築」を目的とするオウンドメディアにおいては、次のような観点が求められます。
| 評価軸 | アクセス数だけで見た場合の限界 | 本質的に見るべきポイント |
|---|---|---|
| 信頼構築の深さ | 一時的な訪問では信頼に直結しない | 滞在時間、読了率、再訪率 |
| エンゲージメントの質 | 表面的な閲覧だけでは関与が浅い | コメント、シェア、回遊率 |
| ビジネス貢献度 | PVが多くてもCVが少なければ成果ゼロ | 資料請求、問い合わせ、売上貢献 |
| ターゲットの一致度 | 無関係な流入が多くても数字は膨らむ | ペルソナとの合致、ニーズとの一致 |
| コンテンツの質 | バズ記事は数字が出やすいが信頼性は不明 | 専門性、独自性、事例性、正確性 |
| メディアの資産性 | 数字はアルゴリズム次第で大きく変動 | 時間が経っても読まれるロングテール記事 |
なぜアクセス数を追うだけでは危険?
ターゲット外のトラフィックが含まれる
SEOやSNSの一時的なブーストでアクセスが増えたとしても、
読者がサービスの見込み客でなければ、成果には結びつきません。
コンテンツの誤解や過信が起きる
短時間で読めるまとめ記事や、センセーショナルなタイトルの投稿はアクセスを集めやすいですが、
それが本当に企業の信頼を高めているのか、検証が必要です。
では、何を見ればいいのか?「信頼資産」としての評価指標
中長期で成果を出すオウンドメディアにおいては、アクセス数以外にも以下のような指標に注目すべきです。
| 指標カテゴリ | 主な項目 | 見るべき意味・意図 |
|---|---|---|
| エンゲージメント | 滞在時間、離脱率、ページ/セッション数、シェア、コメント数 | コンテンツへの関与の深さ・信頼度 |
| コンバージョン | 資料請求、問い合わせ、メルマガ登録 | ビジネス成果への貢献度 |
| ブランド認知・好感 | SNS言及数、アンケート結果、指名検索数 | 認知の広がりとポジティブな印象の定着 |
| 顧客ロイヤルティ | リピート訪問率、継続接触期間、CV後の継続率 | 関係性の持続とファン化の進行度合い |
| 外部評価・信頼性 | 被リンク数、サイテーション、引用媒体数 | 他者からの信用と権威性の可視化 |
短期の数字に振り回されず「積み上げ型」の評価へ
オウンドメディアで信頼を構築するには時間がかかります。
アルゴリズムの変動でアクセス数が減ることもあるでしょう。
でも、以下のような「本質的な成長」は、数字に現れにくいながらも確実に積み上がっています。
- 読者との心理的距離が縮まってきた
- 競合との差別化が言語化できてきた
- 社内のコンテンツ発信体制が整ってきた
資産とは、そうした変化の総体であり、PVの推移グラフには出てこない価値なのです。
よくある誤解と本当のところ
- アクセス数が少ないと、メディアは失敗ですか?
-
違います。少数でも見込み顧客に読まれ、CVや商談につながっていれば成功です。
- トレンド系やバズ狙いの方が数字が出やすいのでは?
-
一時的な効果はありますが、信頼構築や問い合わせ獲得にはつながりにくい傾向があります。特にBtoBでは慎重な選定が必要です。
- 社内でPVばかり求められてつらいです…
-
メディアのKPI設計自体を見直すタイミングかもしれません。CV・読了率・回遊率などの“ビジネス貢献KPI”を提案してみましょう。
まとめ|オウンドメディアのアクセス数に一喜一憂してはいけない理由
あらためて考えてみましょう。
アクセス数は目的ではなく通過点であり、価値の一部にすぎません。
オウンドメディアの本質は「信頼資産の構築」。
誰に、どんな価値を届け、どのような関係性を築いたかこそが、成果そのものです。
アクセス数に一喜一憂せず、数字の奥にある「行動」「信頼」「成果」に目を向ける。
それが中長期で成果を出し続けるオウンドメディア運用の本質です。
 ウェブマーケター
ウェブマーケターお困りの際はぜひ一度ご相談ください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
