オウンドメディア担当者の疑問から引ける!逆引きGA4分析術
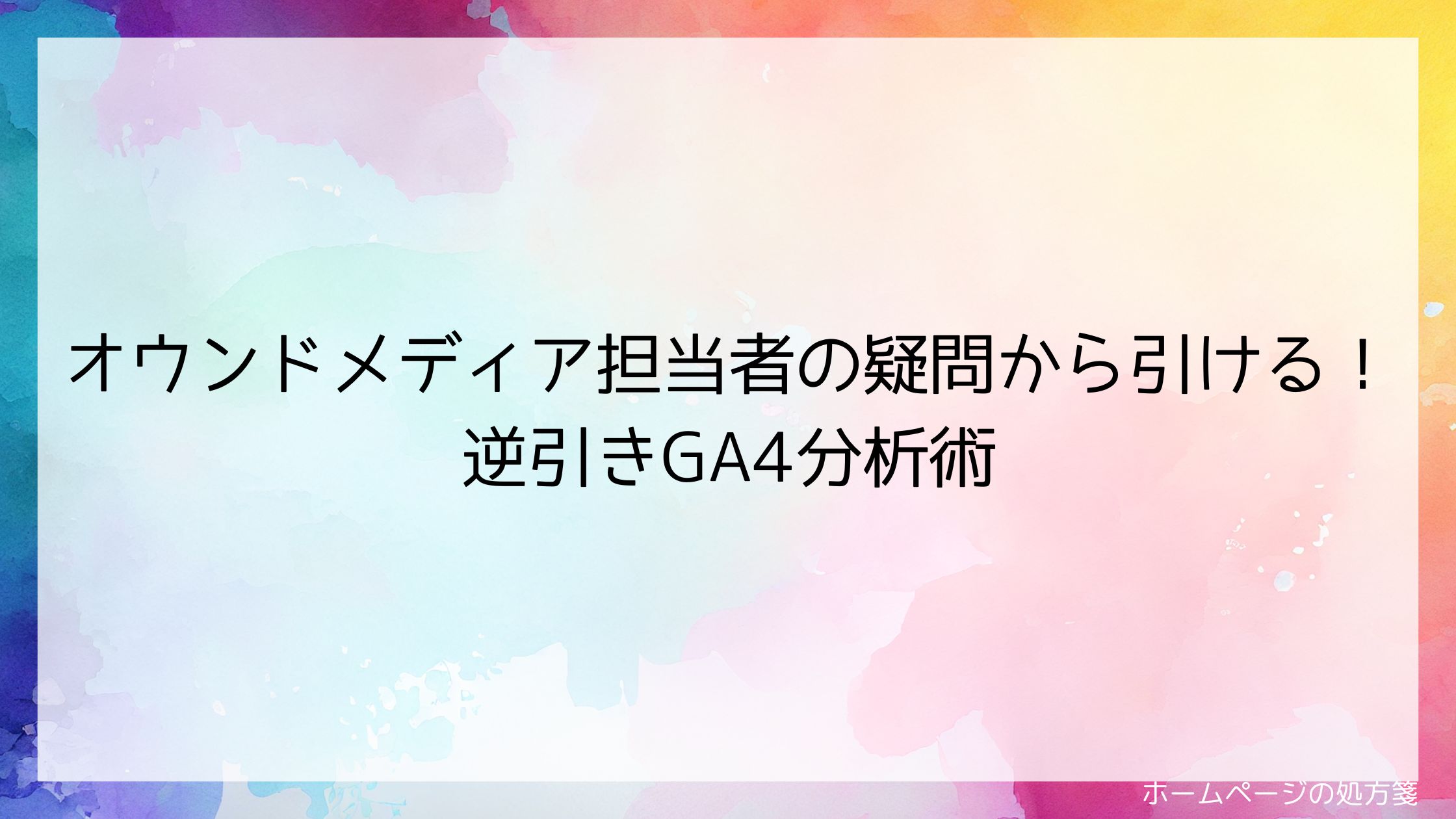
GA4には多くのレポートや指標があるものの、「そもそも何を見ればいいのか分からない」と感じる方は少なくありません。
特に中級者以上の運用者は、「GAの機能を知りたい」ではなく「このことが知りたい」「改善したい」という目的ありきでツールを開くはずです。
この記事では、オウンドメディア担当者がよく抱く具体的な疑問に対して、「どのレポートを見ればいいか」「どのディメンション・指標・イベントを使うべきか」を逆引き形式で紹介します。
どのページから資料請求が多い?
使うレポート:エクスプロレーション > 自由形式 または コンバージョン > イベント
チェックする指標・ディメンション:
- ページパス(
page_path) - コンバージョンイベント名(例:
generate_lead、submit_formなど) - イベント数(
event_count)
どのカテゴリーの記事が長く読まれている?
前提:記事カテゴリをカスタムディメンションで設定している場合
使うレポート:エクスプロレーション > 自由形式
チェックする指標・ディメンション:
- カテゴリ名(例:
content_categoryなど、カスタムディメンション) - 平均エンゲージメント時間(
average_engagement_time) - エンゲージメント率(
engagement_rate)
モバイルとPCで行動に違いはある?
使うレポート:エクスプロレーション > 自由形式 または エンゲージメント > ページとスクリーン
チェックする指標・ディメンション:
- デバイスカテゴリ(
device_category) - ページパス(
page_path) - 平均エンゲージメント時間(
average_engagement_time) - コンバージョン率(
conversion_rate)※設定されていれば
使うレポート:ユーザー > ユーザー属性 > 地域
チェックする指標・ディメンション:
- 地域(
region) - セッション数(
sessions) - 新規ユーザー数(
new_users)
どの記事が最後まで読まれている?(精読率を知りたい)
使うレポート:エンゲージメント > ページとスクリーン
チェックする指標・ディメンション:
- 平均エンゲージメント時間(
average_engagement_time) - エンゲージメント率(
engagement_rate) - ページパス or ページタイトル(
page_path,page_title)
どの筆者の記事が一番読まれている?
前提:筆者名をカスタムディメンションで設定済みの場合
使うレポート:エクスプロレーション > 自由形式
チェックする指標・ディメンション:
- カスタムディメンション:著者名(例:
author_name) - セッション数(
sessions) - 平均エンゲージメント時間(
average_engagement_time)
どの筆者の記事が一番コンバージョンに貢献している?
使うレポート:エクスプロレーション > 自由形式
チェックする指標・ディメンション:
- 著者名(カスタムディメンション)
- コンバージョン数(
conversions) - コンバージョンイベント名(例:
generate_leadなど)
どのSNSからアクセスが多い?
使うレポート:集客 > トラフィック獲得
チェックする指標・ディメンション:
- デフォルトチャネルグループ(
session_default_channel_group) - セッション数(
sessions)
SNSからの流入が多いのはどの記事?
使うレポート:エクスプロレーション > パス分析 または 自由形式
チェックする指標・ディメンション:
- セッション参照元(
session_source)+ ページパス(page_path) - セッション数 or イベント数(
sessions,event_count)
どの都道府県からアクセスが多い?
使うレポート:ユーザー > ユーザー属性 > 地域
チェックする指標・ディメンション:
- 地域(
region) - セッション数(
sessions) - 新規ユーザー数(
new_users)
まとめ|目的から指標を引いて分析を始めてみては?
GA4は機能が多いため、「どこを見ればいいか」で止まってしまうことも少なくありません。
そんなときは、自分の知りたいこと・悩んでいることを出発点にして、そのためのレポートや指標を“逆引き”して使ってみてはいかがでしょうか。
 ウェブマーケター
ウェブマーケターお困りの際はぜひ一度ご相談ください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
