オウンドメディアの広告枠設計の拡大を会社に言われたら
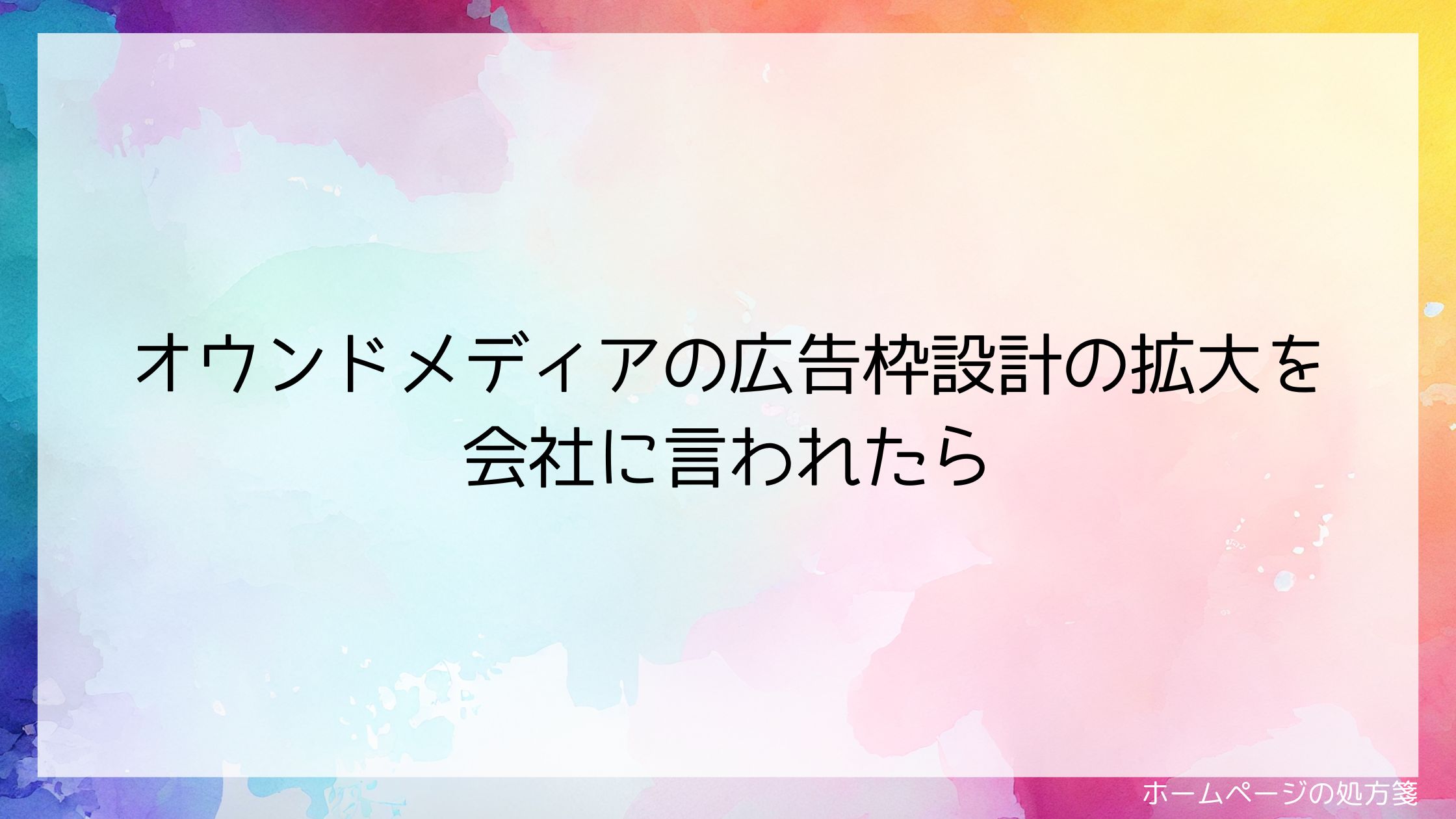
顧客満足か、収益最大化か ― ウェブ担当者のジレンマ
ウェブ担当者として日々の業務に向き合う中で、多くの方が直面する問いがあります。
「もっと広告を増やして、収益を伸ばしたい」
「でも、広告が多すぎるとユーザーが離れていくのではないか」
企業の利益を求める声と、ユーザー体験を損ねたくないという想い。どちらも正しく、しかし両立が難しい。
そんな板挟みに悩む担当者もいるのではないでしょうか。
商売の原点は、お客様第一主義に徹することです。お客様に喜んでいただくこと、お客様に満足していただくこと、それこそが商売の基本であり、もっとも大切なことなのです。
稲盛和夫(京セラ創業者)
本記事では、企業の利益と顧客中心主義のバランスを取りながら成果を出すために奮闘したい担当者に向けて、広告クリックのシミュレーションも交えて
広告エリア枠が大きすぎる場合の3つのリスク~利益主義の弊害~
ユーザーの離脱と信頼喪失
広告の表示面積が増えるほど、コンテンツの可読性や操作性が下がります。
結果として、ユーザーは「このサイトは読みづらい」「信頼できない」と判断し、離脱してしまいます。
これは単なるPV減少ではなく、読者の信用を失うという大きな機会損失です。
Discoverからの除外
Google Discoverは、UXとユーザー満足度を重視したプラットフォームです。
過剰な広告によって滞在時間やエンゲージメントが下がると、アルゴリズム上の評価が下がり、表示されにくくなります。
新規流入の大きな入り口を閉じるリスクがあります。
SNSでのシェア減少
広告過多により、記事の信頼性や読みやすさが損なわれれば、読者は「他人に薦めたくない」と感じるようになります。
SNSでの共有は減り、オーガニックな拡散機会を逃す結果につながります。
UX改善がもたらす価値と長期的インパクト~顧客主義の利点~
広告枠などのUXを改善することで起こりうる効果を短期的・長期的な視点でまとめると以下のようになります。
| 方針 | 短期的な効果 | 長期的な効果 |
|---|---|---|
| 広告面積を広げる | 広告収益が増加しやすい CTRが上がる | 離脱率・嫌悪感の増加 PV減少 ブランド毀損 |
| UXを優先した構成 | 離脱率減 広告収益は控えめ | 再訪率上昇 自然流入増加 信頼によるCV率向上 |
UXを損なうことのリスク
- 滞在時間・再訪率の低下
- 離脱率の上昇と検索順位の低下
- 読了率の低下 → コンバージョン機会の損失
UXを高めることのメリット
- Discoverでの表示機会増加
- SNSでの自然拡散と指名検索増加
- 滞在時間・再訪率の向上
- 結果として広告単価(CPM)やCVRが上昇
ユーザー体験の質が高まることで、広告の「見られ方」や「クリックされ方」も変わり、メディアとしての信頼性と成果の両面が向上します。
顧客満足と企業利益は両立できる
「広告かUXか」ではなく、「UXが広告価値を高める」という視点が重要です。ネイティブ広告やインライン広告など、ユーザーの邪魔にならない設計を工夫すれば、広告収益を損なうことなく顧客満足度を保つことが可能です。
広告占有率とその影響
| 広告占有率 | 想定されるユーザー反応 |
|---|---|
| 約25% | コンテンツの可読性は維持。広告の存在は気になるが許容範囲。UXへの影響は軽微 |
| 約50% | ページの半分が広告になると、読了意欲の低下やスクロール離脱が発生しやすい。SNSでのシェア意欲も減退 |
| 約75% | コンテンツより広告が目立ち、ユーザーは「読まされている」と感じやすい。離脱率・嫌悪感・ブランド毀損リスクが急増 |
広告枠の配置・量の設計は、収益性とユーザー心理のバランスを見極める必要があります。
上司を説得するためのロジック4選
1. 長期的なトラフィック維持が広告価値を支える
広告枠の拡大により一時的にCTR(クリック率)やimp(表示回数)が上がっても、ユーザー離脱が続けば中長期的には広告単価が下がります。
広告ビジネスの基盤は、持続可能なトラフィックです。
ユーザー離脱が続けば、広告単価が下がってしまう理由
広告プラットフォーム(例:Google AdSense)は、ユーザーの行動データをもとに広告の質と掲載面を評価しています。滞在時間が短く離脱が多いサイトは「広告効果が低い」と判断され、表示される広告の質が下がります(=単価が下がる)。また、すぐ離脱されることで広告が十分に表示されず、セッションあたりの収益も減少します。
これが継続すると、サイト全体の広告価値が下がっていく構造になってしまいます。
2. UX改善は検索流入とシェアを促進する
Googleの評価指標(Core Web Vitalsなど)やSNSでの拡散性は、UXに大きく影響されます。
特にCore Web Vitals(Largest Contentful Paint、First Input Delay、Cumulative Layout Shiftなど)は、検索順位に直接関係する重要指標です。読み込み速度や操作のしやすさ、ページの安定性といったUX要素が改善されると、Googleはそのページを「ユーザーにとって価値のあるコンテンツ」と評価しやすくなり、検索結果への露出も高まります。
一方、SNSでは「また読みたい・誰かに紹介したい」と思える体験設計がシェアのきっかけになります。広告が過剰で読むのにストレスがある記事は、たとえ内容が良くても拡散されません。
このように、UXは検索とSNSという2大流入経路に直結する戦略資産といえます。
3. 顧客との関係性がメディアとしてのブランド力を高める
企業の目的は、顧客を創造することである。(ピーター・ドラッカー)
信頼されるメディアであることが、リピート・シェア・紹介を生みます。
短期の利益よりも、顧客との関係性が中長期の収益を支えます。
この信頼が積み重なることで形成されるのが、メディアとしてのブランド力です。
読者が「このサイトの情報なら信用できる」「また読みたい」と思う状態を築くことは、単なる収益向上にとどまらず、検索順位、SNS拡散率、被リンク、認知度といったあらゆる面に波及します。
メディアがブランドを持つということは、「情報を発信すれば届く」状態を意味します。広告単価やCVRを底上げするだけでなく、新たな読者層・協業・採用・営業への効果といった波及的な価値も生まれやすくなります。
4. オウンドメディアの収益化モデル(概算・2パターン)
広告収益を最大化するための設計方針は、ユーザー体験をどこまで重視するかによって大きく異なります。
ここでは、顧客中心主義と利益主義、それぞれのスタンスによる収益の構造的な違いを比較します。
顧客中心主義の場合
UX改善・継続読者重視の場合の収益モデルについて、簡易的にシミュレーションしてみました。
| 指標 | 数値例 |
|---|---|
| 月間PV | 50,000(安定的に維持) |
| 平均CTR(広告) | 1.0%(抑えめ) |
| 平均CPC | 45円(高単価) |
| 月間広告収益 | 約22,500円 |
| 問い合わせなどの副次効果 | 中〜大 |
利益重視の場合
広告面を広く取った短期回収志向
| 指標 | 数値例 |
|---|---|
| 月間PV | 50,000(減少リスクあり) |
| 平均CTR(広告) | 1.5%(高め) |
| 平均CPC | 35円(単価下落リスク) |
| 月間広告収益 | 約26,250円 |
| 問い合わせなどの副次効果 | 低め |
一見、利益重視モデルの方が早く稼げるように見えますが、顧客中心主義モデルのほうがブランド価値・再訪・紹介・採用効果などの無形資産が積み上がり、中長期の回収総額が大きくなる可能性があります。
まとめ:信頼に根ざした設計が、利益を最大化する
広告は必要です。しかし、それ以上に必要なのは「また見たい」「誰かに伝えたい」と思ってもらえるコンテンツと設計です。
もしあなたが会社から「オウンドメディアの広告枠をもっと広げてほしい」と言われた立場だとしたら、今回紹介したようなポイントがユーザー体験と収益性を両立するためのヒントになるかもしれません。
「お客様に満足していただくこと」は、稲盛氏に限らず、松下幸之助やピーター・ドラッカーといった多くの経営思想家が共通して強調してきたテーマでもあります。
ユーザーの体験価値と企業利益の両立は、短期的な売上を超えた、持続的なメディア価値の構築を実現できるのではないでしょうか。
 ウェブマーケター
ウェブマーケターお困りの際はお気軽にお問い合わせください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
