営業・採用リード獲得を目的としたオウンドメディア活用戦略
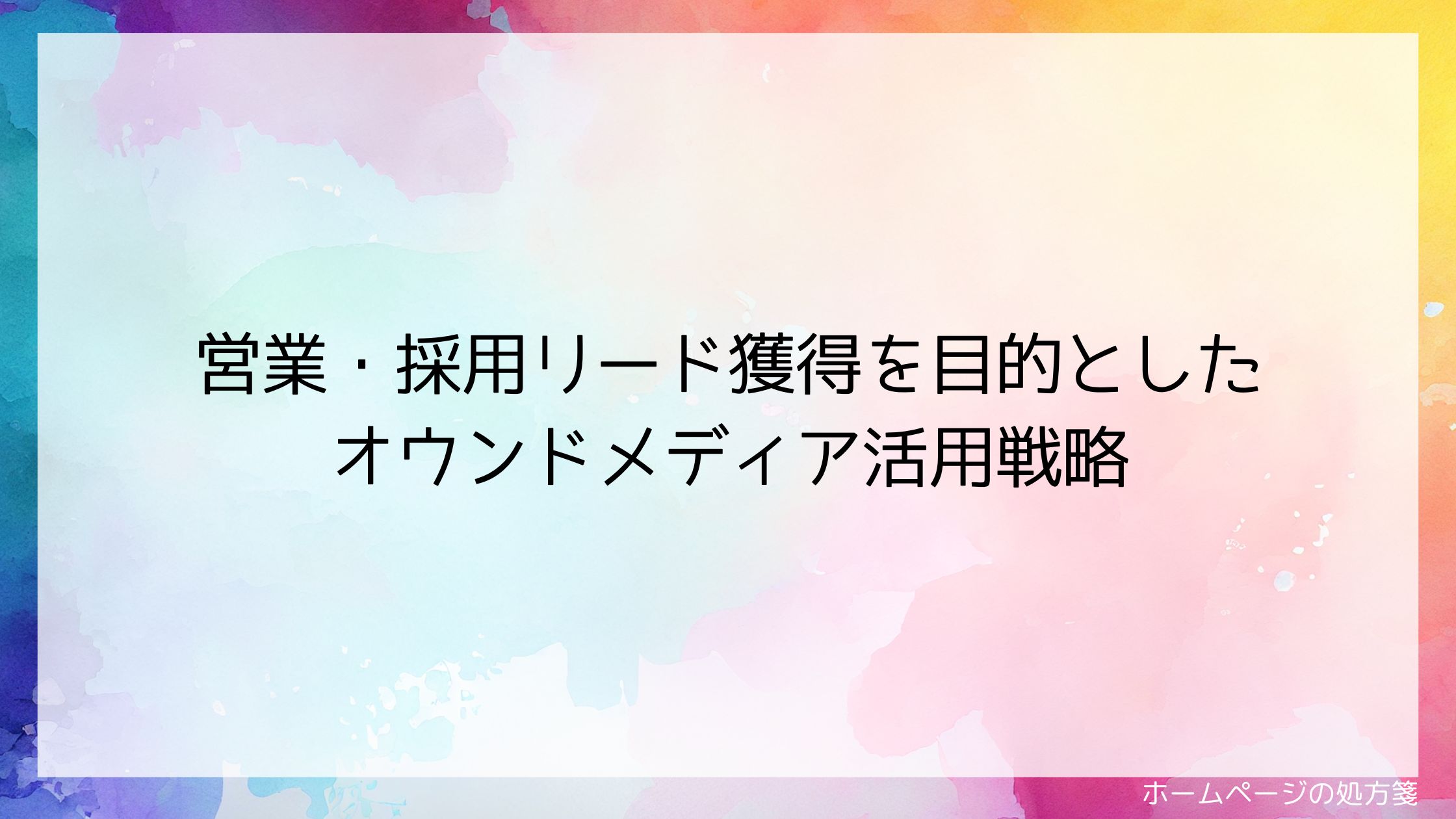
「このメディア、そろそろもっと有効活用できないの?」
そんな上司のひと言から、オウンドメディアの“活かし方”に悩み始めた担当者も多いのではないでしょうか。
アクセス数やPVだけで評価されるのではなく、事業への貢献が求められる時代。採用や営業とどう結びつけるか、明確な設計が必要です。
オウンドメディアを通じて「リードを獲得する」ことは、広告に頼らずに人材採用や営業成果を高める有力な方法です。
リードとは
ここでいうリードとは、将来的に商談・契約・採用といったアクションに至る可能性のある個人や企業の接点のことを指します。
このリードと企業がコミュニケーションを取るための重要な手段の一つが「メールアドレス」です。
リードの質
| 項目 | 質の高いリード | 質の低いリード |
|---|---|---|
| 課題意識 | 自ら課題を認識しており、情報を探している | なんとなく資料を見た/無料だから登録した |
| 関心の深さ | 自社のサービス・文化に一定の理解・共感がある | 興味はあるが理解や比較が浅い |
| 行動履歴 | 関連記事の複数閲覧、資料DL、フォーム送信など具体的な接点がある | 初回アクセスのみ、直帰率が高い |
| 属性のマッチ度 | ターゲット像(職種・業種・スキル・ニーズ)に近い | 自社の提供価値とズレがある属性 |
| 緊急度・検討フェーズ | 検討段階に入っており、短期で動く可能性がある | まだ情報収集中/長期検討中 |
| 返信・対応率 | メール・電話への反応率が高い | フォローしても反応がない/遅い |
獲得したリードを収益につなげるには、「質」と「量」の両面で戦略的なメディア設計が必要です。
本記事では、オウンドメディアによる営業・採用リードの獲得と、その後の成果(KPI・KGI)につながる仕組みを体系的に紹介します。
リードの量と質の最大化戦略~入口・出口の設計がカギ~
では実際に、リードの「量」と「質」をどう高めていくかを考えていきましょう。
その出発点となるのが、ユーザーがサイトに入ってくる入口と、メディアから離脱してアクションを起こす出口の設計です。
単なるコンテンツ制作ではなく、入口(どんな読者に、どんな興味からたどり着いてもらうか)と、出口(どこへ導くか)の戦略設計が重要です。
以下のような視点でUX設計を整理しておくと、読者の体験がスムーズになり、自然にリード獲得につながります。
| 入口(流入経路) | 検索・SNS・外部メディアからどのキーワードや文脈で来るのかを想定。読者の興味・課題に合った導入が必要。 |
|---|---|
| 記事内導線 | 読者の関心が深まる順番でコンテンツを構成し、読み進めやすい構造に。記事下に限らず、文中にもCTAを自然に配置。 |
| 出口(アクション) | 応募・問い合わせ・資料請求など、目的に応じたページやフォームへの導線を分かりやすく明示。UXを損なわない遷移が重要。 |
| メディア外の体験 | エントリーフォームの使いやすさ、資料の中身、レスポンスの早さなど、出口以降の体験設計も成果に直結する。 |
特に出口――つまりメディアを出た後の体験設計(フォーム、ページ遷移、日程調整、資料DLなど)は、収益化する上で最重要ポイントです。
コンテンツ設計:理想の人材・見込み顧客から逆算する
オウンドメディアでは、まず全体のテーマや価値観が伝わる設計が重要ですが、それに加えて「採用目的」「営業目的」に応じた具体的なコンテンツがあると、リード獲得の精度が高まります。
また、読み手が企業に対してどの段階の認知状態にあるかによって、最適なコンテンツの種類も異なります。以下に状況別の適切なコンテンツを整理します。
| 読者の状況 | 営業向けコンテンツ例 | 採用向けコンテンツ例 |
|---|---|---|
| まだ企業を知らない | 業界の魅力やビジョン紹介記事社員の日常紹介コンテンツ | 業界動向・課題に関する解説基礎ノウハウ記事 |
| 認知・関心を持ち始めた | 働く理由・職種紹介カルチャーマッチ診断など | 導入事例の概要紹介FAQ・チェックリスト |
| 検討段階に入っている | 働き方・選考プロセス記事内定者の声 | 詳細な導入事例比較資料・導入フロー説明 |
最近の傾向として、採用でも営業でも「共感」と「透明性」が重視されており、体験ベースのストーリー記事や社員インタビューが効果を発揮しています。
共通して重要なのは、「この会社なら信頼できそう」「もっと話を聞いてみたい」と思わせる関係性構築型コンテンツです。 「この会社なら信頼できそう」「もっと話を聞いてみたい」と思わせる関係性構築型コンテンツです。
CTA設計:自然に、でも確実に次の行動へ誘導する
どんなに良い記事を読んでも、次のステップが分からなければ読者は離脱してしまいます。
読者の心理状態に応じて適切なCTA(行動喚起)を設計することで、成果につながる確率が大きく変わります。
CTAとは
CTAとは、「Call To Action(コール・トゥ・アクション)」の略で、ウェブサイトや広告、メールなどで、訪問者や読者に対して特定の行動を促すためのメッセージや仕掛けのことを指します。
| 読者の状況 | 営業向けCTA例 | 採用向けCTA例 |
|---|---|---|
| 初期接触(認知前〜関心) | LINEで企業の最新情報を受け取る社員紹介記事へ遷移 | 無料ノウハウ資料DL事例記事への内部リンク |
| 関心が高まっている | 説明会申込社員と話せるカジュアル面談予約 | 製品資料請求無料相談の案内バナー |
| 検討段階にある | エントリーフォームへ誘導選考フロー説明記事 | 問い合わせフォームへの誘導見積り依頼ボタン |
メディアの記事を「読んで終わり」ではなく、読み終えたときに具体的なアクションが取れるように、CTAはページの最後だけでなく、記事途中にも自然に差し込むのが効果的です。
成果が出るまでの目安と、追うべきKPI/KGI
どのような成果を目指すかによって、追うべき指標(KPI/KGI)は変わります。
次のように、採用・営業それぞれについて「短期的に追うべきKPI」と「最終的な成果としてのKGI」を明確にすることで、メディア施策の評価がしやすくなります。
| 目的 | KPI(中間指標) | KGI(最終成果指標) |
|---|---|---|
| 営業 | 資料DL数、問い合わせ件数、商談化率、記事滞在時間、フォーム送信率 | 月間/年間売上、商談化件数、受注率、LTV(顧客生涯価値) |
| 採用 | 応募数、説明会参加率、面接設定率、記事閲覧数、CTAクリック率 | 年間採用人数、採用単価の低減、定着率の向上 |
これらを定期的にトラッキングし、特にCTAクリック → アクションまでの遷移率は改善効果が大きい指標です。
特にCTAクリック → アクションまでの遷移率は改善効果が大きい指標です。
よくある失敗と改善の視点
- 自社の紹介ばかりで、読者に響いていない気がします
-
採用・営業においても「読み手にとって価値があるか」が最優先です。自己紹介型ではなく、課題解決やストーリー性を重視した関係性構築型コンテンツに見直すことが必要です。
- CTAは入れているけど、あまりクリックされません
-
単なる「資料はこちら」では動きません。読み手の関心段階に応じた文言・設置場所・形式(ボタン/リンクなど)を調整し、記事内にも自然に組み込む工夫が重要です。
- メディアは読まれているのに、応募や問い合わせが少ないです
-
A. メディアの出口設計に課題がある可能性があります。フォームの導線や遷移先のページ内容を見直し、UXの連続性と心理的ハードルの低減を図りましょう。
- 自社都合の紹介になってしまい、読者に刺さらない
- CTAが弱く、行動の動機を与えられていない
- UX設計が分断していて、せっかくの関心が離脱につながる
まとめ:企業の「選ばれる力」を育てるオウンドメディアへ
採用や営業の現場において「企業の魅力や強みをどう伝えるか」は永遠の課題です。 オウンドメディアを通じて、接点を増やし、関係性を育み、信頼を蓄積することが、最終的には応募や問い合わせという成果につながっていきます。
「集客」だけではなく、「関係性の設計」に力を入れたメディアづくりを、今日から始めてみてはどうでしょうか?
 ウェブマーケター
ウェブマーケターお困りの際はお気軽にお問い合わせください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
