BtoBマーケティングの新常識:業界の常識を疑い、お客様目線を最優先にする
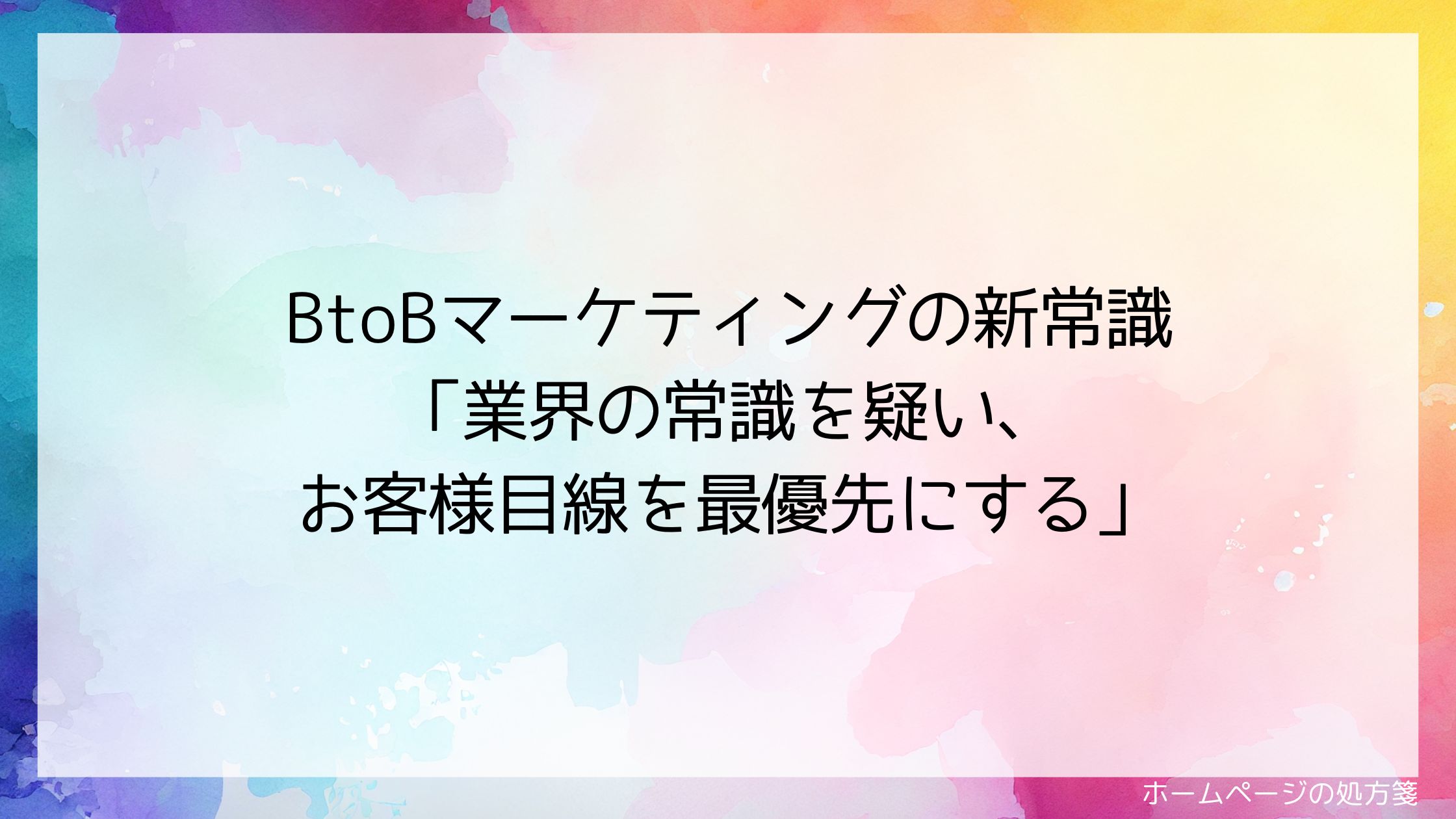
「業界ではこれが当たり前」
「今までこうだったから」
皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
BtoBマーケティングの世界では、業界ごとの慣習や常識が根強く存在します。
しかし、こうした「当たり前」に縛られていては、真の顧客価値を見失い、市場での差別化が困難になってしまいます。
 ウェブマーケター
ウェブマーケター本記事では、私がコンサルタントとしてクライアント企業に提案している「業界の常識を疑い、お客様目線で判断する」というアプローチと、マーケティング責任者と運用担当者それぞれが担うべき役割について解説します。
なぜ「業界の常識」を疑う必要があるのか
多くの企業が無意識に従っている「業界の常識」には、以下のような問題があります。
- 時代遅れの慣習が残りやすい
かつては合理的だった方法が、環境変化により非効率になっていることがあります。 - 顧客の本質的なニーズを見逃す
「業界ではこうするもの」という思考が、本当の顧客課題の理解を妨げます。 - 差別化の機会を逃す
全社が同じ常識に従えば、必然的に類似したサービスが増え、競争優位性を築けません。
一方で、「お客様目線」を基準にすることで、以下のメリットが生まれます。
- 本質的な価値提供
業界の慣習ではなく、顧客の真の課題解決に焦点を当てられます。 - 独自のポジショニング
顧客視点から再構築されたサービスは、自ずと差別化されます。 - 長期的な顧客関係の構築
顧客の成功を最優先にすることで、信頼関係が深まります。
それでは、この考え方を実践するために、マーケティング責任者と運用者がそれぞれどのような役割を担うべきか見ていきましょう。
マーケティング責任者の役割:常識を超えるためのリーダーシップ
「業界ではこれが当たり前」という思い込みの定期的な検証
マーケティング責任者は、組織内に存在する「当たり前」の思い込みを定期的に洗い出し、検証する必要があります。
- 四半期ごとの「常識疑問会議」を開催し、「なぜそうしているのか」を徹底的に問いかける
- 「〇〇だから」「業界ではこうするものだから」という理由付けを禁止し、顧客価値の観点からの説明を求める
- 異業種からゲストを招き、外部視点での評価を受ける機会を設ける
「当たり前」と思われていた慣行の中から、実は顧客にとって価値のないものが浮き彫りになることがあります。
顧客企業の課題解決を優先する意思決定
マーケティングの意思決定において、「社内の都合」や「業界の慣習」よりも、「顧客の課題解決」を最優先にする文化を作ります。
- 企画・戦略会議ではず「これは顧客のどんな課題を解決するか」という問いかけから始める
- 提案された施策に対して、「顧客視点での価値」を数値化する評価基準を設ける
- 「売上向上」だけでなく「顧客の成功」を重要なKPIに設定する
顧客の課題解決を最優先にすることで、結果的に持続可能な売上成長につながります。
短期的な売上だけを追求する思考とは一線を画すことが重要です。
運用者がユーザーの声を拾いやすい環境や部門間調整を行う
マーケティング責任者は、運用者が顧客の生の声に触れる機会を増やし、その声をマーケティング活動に反映しやすい環境を整える必要があります。
- 営業・サポート・開発など各部門を巻き込んだ「UX改善会議」を定期的に開催する
- マーケティング担当者が定期的に顧客訪問や商談同席をする制度を設ける
- 顧客の声の共有プラットフォームを構築し、全社で閲覧・活用できるようにする
部門間の壁を低くし、顧客の声が自然と組織全体に浸透する仕組みを作ることが、マーケティング責任者の重要な役割です。
マーケティング運用者の役割:顧客理解を深める
競合サイト分析
競合分析は、単なるベンチマーキングにとどまらず、業界の常識を見つけ出し、それを超える機会を発見するプロセスです。
- 直接的な競合だけでなく、顧客が「同じ課題を解決するために利用する可能性のある代替手段」まで広げて分析する
- 競合の「やっていないこと」に特に注目し、その理由を深掘りする
- 競合サイトのユーザビリティテストを実施し、顧客目線での使いやすさを客観的に評価する
業界標準を超えるためには、まず業界標準を正確に把握することが重要です。
ユーザーインタビュー(関係構築)
数値データだけでは見えてこない顧客の本音や潜在ニーズを掘り起こすには、直接インタビューをすることが近道です。
- ターニングポイントを引き出す質問を心がける
(例:この商品を知ってから、決めるまでの経緯で何が決め手になったのか) - インタビューで得た結果をフィードバックする循環を作る
顧客との深い関係構築を行い発信するコミュニケーションを改善していくことで、顧客は「この会社は本当に自分たちのことを理解している」と感じやすくなります。インタビューは手間こそかかりますが、長期的な関係性を築くのに有効な手段です。
顧客目線のマーケティングを実践するために
ここまで述べてきた考え方を組織に定着させるには、具体的なステップを踏むことが重要です。
- 自社のマーケティング活動において「当たり前」とされていることをリストアップする
- それぞれの「当たり前」について、「なぜそうしているのか」を徹底的に問いかける
- 顧客価値に直結していない「常識」を特定し、社内で共有する
- 顧客インタビュー、アンケート、行動データ分析などを組み合わせて顧客理解を深める
- 顧客が意識していない、潜在的なニーズや課題を発見する
- 顧客のユーザー体験に焦点を当て、体験全体を把握する
- ステップ1で特定した「疑うべき常識」と、ステップ2で発見した「真のニーズ」をもとに、新しいアプローチを設計する
- 小規模な実験から始め、顧客の反応を確認しながら段階的に拡大する
- 成功事例を社内で共有し、「顧客目線で考えることの価値」を実証する
まとめ:顧客目線のマーケティングがもたらす真の競争優位性
「業界の常識を疑い、お客様目線で判断する」というアプローチは、単なるマーケティング戦術ではなく、ビジネス全体の哲学と言えるものです。
マーケティング責任者には、組織の思考の枠組みを変え、顧客価値を最優先する文化を醸成するリーダーシップが求められます。一方、マーケティング運用者には、日々の活動の中で顧客の声に耳を傾け、その洞察を具体的な改善につなげる実践力が不可欠です。
両者が緊密に連携し、「業界ではこうするものだ」という思い込みから解放されたとき、真に顧客に寄り添ったマーケティングが実現します。そして、それこそが模倣困難な競争優位性をもたらすのです。
この記事が、皆さんのマーケティング活動に新たな視点をもたらし、顧客との関係をより深めるきっかけとなれば幸いです。



この記事は、ウェブコンサルタントの井水朋子による連載「BtoBウェブマーケティングの新常識」の一部です。戦略立案から実行サポートまで、伴走型のコンサルティングを提供しています。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
