マーケティング「3-3-3ルール」の多様な解釈と自社に活かすヒント
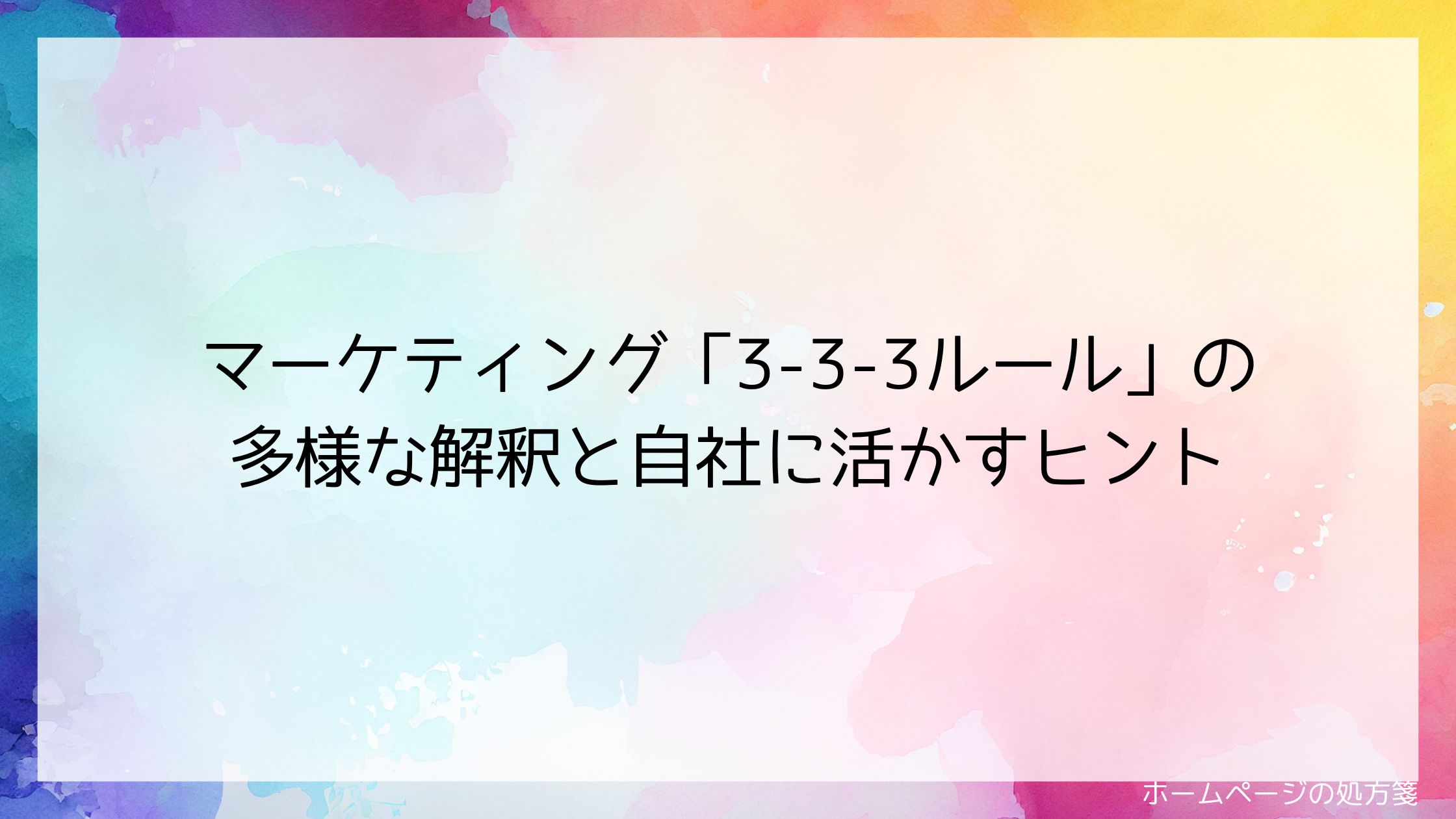
マーケティングの世界って、本当にたくさんの情報やノウハウで溢れていますよね。
特に、マーケティング戦略や施策の「型」や「ルール」のようなものが語られるとき、それがまるで唯一の正解かのように聞こえてしまうこともあります。
そんな中で、まことしやかに囁かれる3-3-3ルール。
実はこのルール、非常にシンプルで分かりやすい指針として語られることが多いのですが、人によって、あるいは文脈によって、指している内容が結構違うんです。
今日は、そんな掴みどころのない「3-3-3ルール」について、よく語られる5つの解釈を紹介します。
3-3-3ルールとは
3-3-3ルールは、特定の誰かが提唱した明確な定義があるわけではなく、様々なマーケターやビジネスパーソンが、経験則や覚えやすい目安として語ってきたものが集まったような概念です。
だからこそ、色々なバリエーションが存在します。
ここでは代表的な5つの解釈を見ていきましょう。
解釈1:戦略的フレームワーク(期間・メッセージ・プラットフォーム)
戦略的フレームワークの3-3-3ルール
マーケティングのキャンペーン計画を立てるとき、「あれもこれも」と手を広げすぎて、結局どれも中途半端…なんてこと、ありませんか?
この考え方は、計画を「3つの期間」「3つの主要メッセージ」「3つの主要プラットフォーム」という3つの核となる要素に絞り込んで、戦略をシンプルかつ強力にするためのフレームワークです。
なぜ「3」に絞るの?
狙いは、リソース(人、時間、お金)を集中させること。そして、チーム内での目標共有を簡単にし、効果測定も分かりやすくすることです。「選択と集中」で、キャンペーンの焦点を明確にするんですね。
構成要素を見てみよう
- 期間
キャンペーンを段階に分けます。
例えば、「①知ってもらう(認知)」「②興味を持ってもらう(エンゲージメント)」「③行動してもらう(コンバージョン:問い合わせや購入など)」のように、顧客の気持ちの変化に合わせてアプローチを変えていきます。 - 主要メッセージ
キャンペーンで一番伝えたい核となるメッセージを3つに絞ります。
「私たちの商品は、[顧客の悩み]を解決し、[独自の価値]を提供し、[理想の未来]を実現します」のように、ストーリーの骨組みを作るイメージです。分かりやすく、心に響き、行動につながるメッセージが理想です。 - プラットフォーム
どのチャネル(SNS、Web広告、ブログ、メールマガジンなど)に注力するかを3つ選びます。ターゲットが多く利用していて、メッセージが効果的に伝わる場所を選び抜くことが重要です。広く浅くではなく、選んだ場所でしっかり存在感を出すことを目指します。
シンプルさのメリットと注意点
この考え方を使うと、複雑な計画がスッキリ整理され、やるべきことが明確になります。
ただ、「3」という数字にこだわりすぎると、「実は4つ目のプラットフォームに重要なお客さんがいた」「伝えるべき大事なメッセージがもう一つあった」ということを見逃してしまう可能性も。
あくまで、戦略を整理するための「目安」や「ヒント」として捉え、自社の状況に合わせて柔軟に考えましょう。
解釈2:アテンションスパン・フレームワーク(3秒・3分・3時間)
アテンションスパン・フレームワークのの3-3-3ルール
情報があふれる現代、人の注意力はどんどん短くなっていると言われます。スマホをスクロールする指は、一瞬で次の情報へ…。
この考え方は、そんなユーザーの注意を引きつけて行動を促すまでのプロセスを「最初の3秒」「次の3分」「最後の3時間」という時間軸で捉えるフレームワークです。
まさにマーケティングは「時間との戦い」だ、という認識に基づいていますね。
なぜ時間が重要?
Webサイトや広告、SNSの投稿を見たユーザーは、最初の「3秒」で「これは自分に関係あるか?」「もっと見る価値があるか?」をほぼ無意識に判断すると言われています。
ここで興味を引けなければ、どんなに良い情報や商品も、その存在にすら気づいてもらえないかもしれません。
構成要素を見てみよう
- 3秒(注意を引く)
スクロールする指を止めさせる「フック」の部分です。インパクトのある見出し、魅力的な画像や動画の冒頭、共感を呼ぶ問いかけなどで、「おっ?」と思わせることが最重要課題です。意外性や、ユーザーが感じている悩みに直接訴えかけるのも効果的です。 - 3分(興味を育てる)
注意を引いた後、短い時間で「なるほど」「もっと知りたい」と思わせ、信頼感を育てる段階。役立つ情報、分かりやすい説明、共感できる短いストーリー、統計データなどを提供します。専門用語を避け、読みやすい、語りかけるようなトーンが好まれます。 - 3時間(行動を促す)
これは実際の3時間というより、「ユーザーが情報を比較検討し、納得して、最終的に行動(問い合わせ、資料請求、購入など)を決めるまでの思考・検討期間」というイメージです。この段階では、分かりやすい行動への誘導(「詳しくはこちら」ボタンなど)や、迷っている人の背中を押す情報(限定オファー、お客様の声、導入事例など)が効果を発揮します。適切なタイミングでのフォローアップも含まれるかもしれません。
「3秒ルール」との関係は?
Webマーケティングでよく言われる「3秒ルール」(Webサイトは最初の3秒で判断される)は、このフレームワークの最初のステップとほぼ同じ考え方です。
この解釈の特徴は、その「3秒」で終わりではなく、「注意→興味→行動」という一連の流れを設計しようとしている点。単に離脱を防ぐだけでなく、その後のエンゲージメント(関わり)まで見据えた、より広い視点を提供してくれます。最初の3秒の工夫はもちろん大事ですが、その後の「3分」「3時間」のステップも意識して設計することが、成果につながる鍵となりそうです。
解釈3:メッセージング・フレームワーク(簡潔性と構造)
メッセージの3-3-3ルール
伝えたいことがたくさんあると、つい情報を盛り込みたくなりますが、全部を詰め込むと、かえって一番伝えたいことがぼやけてしまう…。
この考え方は、マーケティングメッセージを意図的に短く、シンプルに構成することで、最大限のインパクトと分かりやすさを追求するアプローチです。まさに「Less is more(少ない方が豊かである)」の精神ですね。
なぜシンプルさが大事?
繰り返しになりますが、ユーザーが情報に集中できる時間は非常に限られています。だからこそ、メッセージは「パッと見て、すぐわかる」ことが重要になります。核心を突いた短い言葉の方が、忙しいユーザーの記憶に残りやすいのです。
構成要素の例
この考え方は、コピーライティングなどの場面で、例えば以下のような具体的なルールとして語られることがあります。
- 見出しは「3語」で
インパクトを最大化し、一瞬で内容を伝える。 - 本文は「3文」で
伝えたいことの要点を、簡潔明瞭な3つの文でまとめる。 - CTA(行動喚起)は「3つの箇条書き」で
行動するメリットや理由を、分かりやすく3点に絞って提示する。
補足:別の情報源では「1文を最大3語で。キーポイントは3つに絞る」という、さらにストイックなルールも提案されているようです。
実用上の注意点
「見出しは絶対に3語じゃないとダメ!」のように、数字そのものにガチガチに縛られる必要はありません。これはあくまで、「簡潔さ」と「分かりやすさ」という目標を達成するための、覚えやすいガイドラインと捉えるのが良いでしょう。
解釈4:ソーシャルメディア・フレームワーク
SNSマーケティングの3-3-3ルール
SNSマーケティングを始めるとき、「どのSNSを使うべき?」「どれくらいの頻度で投稿すればいいの?」と、悩みは尽きませんよね。この「3-3-3ルール」は、ソーシャルメディア戦略に関しても、いくつかの異なるアプローチとして語られています。
- タイプA(存在感と頻度重視)
ターゲット顧客が集まる「3つの主要なSNS」を選び、そこに存在感を示す。そして、「週に3回」は投稿やユーザーとの交流(エンゲージメント)を行い、コンテンツも「3つの異なる形式」(例:テキスト投稿、画像、ショート動画など)を使い分ける、という考え方。継続的な情報発信で、顧客の記憶に残り続ける(Top of mind)状態を目指します。 - タイプB(チャネル優先順位付け): やみくもに多くのSNSに手を出すのではなく、自社の目的やターゲット層をしっかり調査した上で、「最も重要なSNSトップ3」を戦略的に選びます。さらに、将来的な変化にも備えて「次に重要なSNSトップ3」(セカンダリ)も特定しておく、というチャネル選択の考え方です。
どちらの考え方を参考にすべき?
もしあなたが「どのSNSを使うべきか、選択に迷っている」なら、タイプBの優先順位付けの考え方が、戦略を立てる上で役立つでしょう。
もし「使うSNSはある程度決まっているけど、どう運用すれば効果的なのか分からない」という状況なら、タイプAの頻度や形式の考え方が、日々の運用ルールの参考になるかもしれません。
もちろん、これらは組み合わせることも可能です。タイプBで選んだトップ3のSNSで、タイプAの運用ルール(週3回、3フォーマットなど)を試してみる、といった形です。いずれにしても、自社の目的とリソースに合わせて「選択と集中」を行うことが、SNSマーケティング成功の鍵と言えそうです。
あなたのビジネスに合う「3-3-3ルール」はありましたか?
さて、5つの異なる「3-3-3ルール」の解釈を見てきました。いかがでしたか?
「なるほど、こういう考え方もあるのか」「うちのビジネスだったら、このルールが参考にできそうだ」と感じたものはあったでしょうか。
ここで大切なのは、これらのルールは絶対的な正解ではないということです。
今回ご紹介した「3-3-3ルール」は、あくまで先人たちの経験から生まれた「目安」や「思考のヒント」の一つです。そのまま当てはめるのではなく、「なぜ3秒なのか?」「なぜ3回なのか?」とその背景にある意図を考え、自社の状況に合わせてカスタマイズしていくことが重要です。
このように、「3-3-3ルール」は英語圏のマーケティングやビジネスの文脈で時折使われる言葉ですが、その意味するところは非常に多様です。
もしあなたが誰かから「マーケティングの3-3-3ルールって知ってる?」と聞かれたら、「どの3-3-3ルールのことですか?」と聞き返してみるのが安全策です。安易に「ああ、あれですね」と答えてしまうと、話が噛み合わなくなってしまう場合があるのでご注意を。
大切なことは、「3-3-3ルール」でマーケティング活動の行動指針を明確にすることです。
自社の3-3-3ルールを作ってみてはいかがでしょうか。
 ウェブマーケター
ウェブマーケターお困りの際はぜひ一度ご相談ください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
