BtoBウェブマーケティングで挑戦的目標を達成するためのチームビルディング
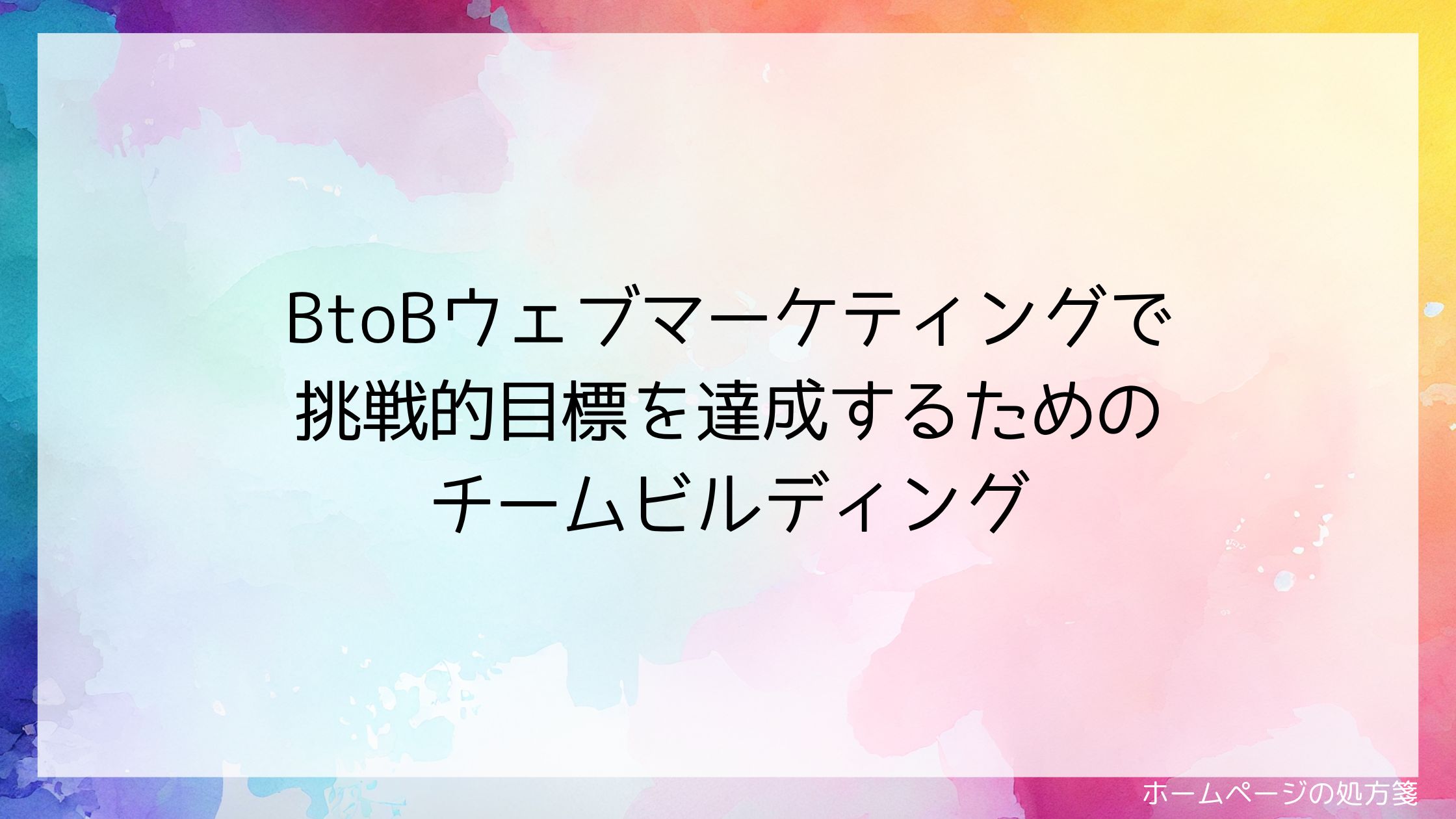
リスクをとってこそ、利益が見込める
BtoBマーケティングの世界では、「安定」を求めるあまり新しい挑戦を避け、結果として競合他社に遅れを取るケースが多く見られます。
しかし、ビジネスの本質を考えれば、リスクをとってこそ、利益が見込めるのです。
 ウェブマーケター
ウェブマーケター本記事では、挑戦的な目標に向かって効果的に機能するマーケティングチームの構築方法と、管理者と運用者それぞれがどのようにふるまうべきかについてご紹介します。
リーダーもメンバーも挑戦的目標に取り組めない3つの状況
BtoBマーケティングで挑戦的な目標達成を阻む典型的なシナリオを理解することが重要です。以下に、組織のマインドセットから具体的な行動パターンまで、多くの企業であるあるの問題を紹介します。1つでも当てはまるものがあれば、改善が必要です。
企業のマインドセットの問題
- 「前例がない」という拒絶反応
- 全額消化を求める文化
- 短期的KPIへの固執
評価と文化の問題
- 失敗をネガティブな評価としてメンバーに負わせる
- 挑戦事例とその成果を共有・称賛する機会の不足
- メンバーの挑戦意欲を活かす文化がない
具体的な行動パターン
- 完璧主義による実行の遅延
- データよりも直感が優先される
- 分からないことはやらない姿勢
- 部門間の縄張り意識縄張り意識
これらの課題を乗り越えるには、管理者と運用者それぞれが適切なふるまいを実践し、挑戦を奨励するチーム文化を構築することが不可欠です。では、具体的にどのような態度や行動が効果的なのでしょうか。
マーケティング管理者はどのようにチームに貢献するのが理想的か
挑戦を奨励する環境をつくる
- メンバーの心理的安全性の確保する
チームメンバーが意見やアイデアを自由に発言できる場を作り、「変な質問」や「失敗」を恐れない雰囲気を醸成する - 投資ポートフォリオの設計する
予算の70~80%を確実性の高い施策に、20~30%を実験的な新規施策に配分する原則を確立する - 長期的視点を明確にする
短期的なROIだけでなく、1-3年の時間軸でのブランド価値や市場ポジションの向上を評価指標に加える
実験枠の予算を作る
- 実験予算の明確化
年間マーケティング予算の20-30%を「実験枠」として明示的に設定し、チームに裁量権を与える - 段階的挑戦の奨励
新規施策は小規模テスト→中規模展開→全面展開というステップを踏み、各段階で明確な評価と承認を行う - 失敗の再定義
失敗を学びを得るプロセスとして位置づけ、最大許容損失額を事前に設定することで、心理的負担を軽減する
実験予算を「使い切らなければならないもの」と捉えず、効果的な施策が見つかった場合には柔軟に追加投資できる体制を整えることが重要です。
失敗を許容し学習する組織文化の醸成
- 自らの失敗と学びの共有: 管理者自身が過去の失敗体験とそこから得た教訓を積極的に共有する
- 評価基準の多様化: 単純な成果指標だけでなく、「学習の質」や「挑戦の度合い」も評価項目に含め、公平に評価する
- 質問と対話の促進: 「なぜそう考えるのか」「他の選択肢はあるか」といった質問を通じて、チームの思考を深める習慣をつける
「失敗」と「単なる実行ミス」は区別すべきです。挑戦的な目標設定の下での計画的な施策実行と検証が伴う失敗は価値あるものとして評価し、単なる準備不足や思考停止による失敗は改善機会として建設的にフィードバックしましょう。
管理者のふるまい方が明確になったところで、次は実際に施策を実行する運用者がどのようにふるまうべきかを見ていきましょう。
マーケティング運用者はどのようにチームに貢献するのが理想的か
管理者が環境を整える一方で、実際に施策を実行し、日々の運用を担うのが運用者です。
挑戦的な目標達成のために、運用者はどのようにふるまうべきでしょうか。
好奇心と学習意欲の維持
- 定期的に自己研鑽する
自らのスキルと知識を更新し続ける - 「知らない」を認める
わからないことを素直に認め、質問や学習の機会として捉える姿勢を持つ - 仮説思考を習慣にする
なぜこの施策が効果を生むと考えるのか、検証可能な形で仮説を立てる
小さく始めて、素早く学ぶ
新しい施策の導入にはリスクが伴いますが、そのリスクを最小化しながら最大の学びを得る姿勢が重要です。
- 実験マインドセットの採用
新しい施策を「完璧な成功を目指す本番」ではなく「学びを得るための実験」として捉える - MVP(最小限の実用製品)アプローチ
完璧を求めず、検証に必要な最小限の機能や内容で素早くテストし、反応を見る - データに基づく意思決定
直感や思い込みではなく、A/Bテストなどの客観的なデータを重視した判断を行う
テストの目的は「正しさの証明」ではなく「学びの獲得」です。
「これが失敗したらどう学ぶか」という視点も事前に考え、どんな結果になっても価値を見出せる設計を心がけましょう。
透明性の高いコミュニケーション
実験と学習のサイクルを効果的に回すには、オープンなコミュニケーションが不可欠です。
- 早期の情報共有
問題や失敗の兆候を感じたら、すぐに管理者やチームメンバーと共有し、早期対応を可能にする - 構造化された振り返り
施策終了後に「何を期待していたか」「実際に何が起きたか」「なぜその差が生じたか」「次に活かせる教訓は何か」を整理して共有する - 水平的な知識共有
同僚との定期的な事例共有会を自主的に開催し、個人の学びをチーム全体の財産にする
効果的な共有方法
「何がうまくいかなかったか」だけでなく「何を試みたのか」「なぜそう考えたのか」という思考プロセスも含めて共有することで、チーム全体の判断力向上につながります。
運用者と管理者それぞれのふるまい方を理解したところで、最後に両者が効果的に協働するための方法について考えてみましょう。
挑戦的目標を達成する効果的なチームコミュニケーション
管理者と運用者がそれぞれの役割を理解し実践することも重要ですが、両者が効果的に連携することで、初めてチームとしての力を最大化できます。
定期的な対話と相互理解
- 1on1ミーティングの活用
管理者と運用者の間で週次や隔週の1on1ミーティングを設け、業務上の課題だけでなく、キャリア目標や学習ニーズも共有する - チーム振り返りの習慣化
四半期ごとに全体戦略を見直す機会を設け、全員が率直に意見を述べられる場を作る - 相互フィードバックの奨励
管理者から運用者へのフィードバックだけでなく、運用者から管理者へのフィードバックも積極的に行う文化を構築する - チーム全体で挑戦を称賛する機会
挑戦的な取り組みや学びの共有を公式に称賛・表彰する場を設け、挑戦の価値を可視化する
共通の評価基準と期待値の設定
協働を効果的に進めるには、明確な共通理解を持つことが不可欠です。
- 「挑戦」の定義を共有する
チームとして何を「価値ある挑戦」と考えるのかを明文化し、共通認識を持つ - 短期と長期のバランス
短期的な成果指標と長期的な価値創造の両面から評価する体系を構築し、透明性を確保する - 失敗からの学びを可視化する
「失敗」を「学びがなかった取り組み」と再定義し、どんな学びが得られたかを評価の中心に据える
これらのコミュニケーション方法を実践することで、管理者と運用者の間に信頼関係が生まれ、挑戦的な目標に向かって一体感のあるチームが形成されます。
まとめ:挑戦的目標を達成するBtoBマーケティングチームの構築
ここまで、BtoBウェブマーケティングにおける管理者と運用者それぞれのふるまい方、そして効果的なチームコミュニケーションについて見てきました。最後に、全体を通してのポイントをまとめます。
挑戦的な目標を達成するBtoBマーケティングチームの構築には、管理者と運用者それぞれが適切なマインドセットと行動様式を持つことが不可欠です。管理者は心理的安全性を確保し、適切なリスクテイクを奨励する環境を整える。
運用者は好奇心と学習意欲を持ち、「小さく始めて素早く学ぶ」姿勢で日々の業務に取り組む—この両輪がうまく回ることで、チームとしての創造性と実行力が高まります。
重要なのは、「失敗」を避けるべき悪ではなく、成長のための必要なステップとして捉え直すことです。
計画的に小さなリスクを取り、そこから得られた学びをオープンに共有し次の施策に活かす—この循環をチーム文化として定着させることが、挑戦的な目標を達成するBtoBウェブマーケティングチームの真の競争力となるでしょう。
重要なのは、「失敗」を避けるべき悪ではなく、成長のための必要なステップとして捉え直すことです。



この記事は、ウェブコンサルタントの井水朋子による連載「BtoBウェブマーケティングの新常識」の一部です。戦略立案から実行サポートまで、伴走型のコンサルティングを提供しています。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。専門家と一緒に作業すれば、余計な遠回りをせずに成果へ近づけるはずです。
